医学講座
手稲鉱山の歴史
今日は2024年12月12日(木)です。
休診日で一日中家にいました。
北海道新聞電子版に私が子供の頃に住んでいた手稲鉱山のことが出ていました。
私は1961年に手稲西小学校に入学しました。
同じ場所に手稲西幼稚園もありました。
どちらも手稲町立でした。
昔は札幌市ではなく、札幌郡手稲町でした。
■ ■
北海道新聞電子版の記事です。
連載<ディープに歩こう_札幌・手稲編>は札幌市手稲区をディープに歩きます。
11月最後の日曜日となった24日、札幌市手稲区のJR手稲駅南口に止まった1台の路線バスの行き先表示を男性が見つめていた。
男性は、札幌市南区在住の土木コンサルタント石川成昭(しげあき)さん(62)。バスは山あいの終点「手稲鉱山」と駅を結ぶ、ジェイ・アールR北海道バスの手稲鉱山線。「閉山から半世紀以上、この名前で残っていたのが奇跡」。12月ダイヤ改正で手稲金山線に変わった。

金山地区にかつてあった手稲鉱山は金鉱として知られ、石川さんの曽祖父貞治(ていじ)さんが名付けたとされる。
1940年(昭和15年)ごろに発行された「手稲鉱山史」によると、貞治さんが16年(大正5年)に開発に手を染めたとあるが、「その後は、一財産を失った」と石川さん。そんな曽祖父の姿を見てきたためか、祖父は大学卒業後、当時の鉄道省に入庁した。「ヤマ師はだめだ。堅実に働け」。祖父から繰り返し言われたという。
石川さんは大学卒業まで東京で過ごし、道内の企業に就職。会社員の傍ら、2年前から夕張市石炭博物館の館長も務める。「夢を追う冒険家だった曽祖父に呼ばれたかな」と笑う。
貞治さんは島根県に生まれ、札幌農学校(現北大)を経て北海道庁に入った。退職後は、札幌で現在のコンサルタント業となる鉱農商議館の看板を掲げ、各地の油田や炭鉱など地下資源開発に投資した。
手稲山では1890年代から鳥谷部弥平治(とりやべやへいじ)が採掘を手がけるも、有望な金脈が見つからず1907年(明治40年)ごろに断念したと伝わる。
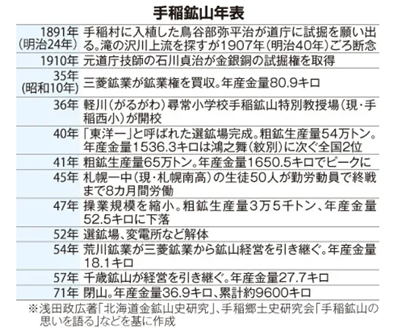
3年後、貞治さんは、現在の経済産業省の地方組織となる札幌鉱山監督署から試掘権を取得し、後を引き継ぐ形で開発に乗り出した。2万5千円(現在の3千万円程度)を投資したが、採算に合わず20年に試掘権を手放した。
金の含有量は鉱石1トンに対し3グラム程度とされる。採算ベースに乗せるには多額の投資による大規模開発が不可欠だ。手稲鉱山で本格的な採掘作業が始まったのは、財閥の三菱鉱業(現三菱マテリアル)が鉱業権を取得した35年(昭和10年)以降となる。
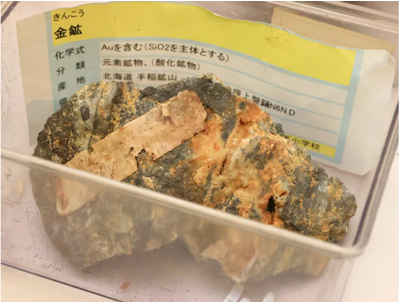
1940年には、東洋一と称された月5万トンの鉱石を処理できる「選鉱(せんこう)場」が完成。産金量は1536.3キロと5年間で19倍に激増し、作業員の数も200人台から2000人近くに増えた。
しかし、太平洋戦争末期に入り貿易が滞ると、資源獲得の決裁手段としての金の重要性は低下する。43年には、加工しやすく導電性が高い銅の生産に改められた。作業員の多くが兵士として召集され、道内に強制連行された朝鮮人労働者と勤労動員の学生が代わりを務めた。

1945年1月8日、旧制札幌一中(現・札幌南高)3年生だった、元小学校長の小山田碩(せき)さん(95)=札幌市南区=は、猛吹雪の中、級友45人と鉱山に到着した。翌日から午前5時起床の寮生活が始まった。職場は選鉱場。掘り出された鉱石から金属成分を取り出す仕事だった。
物資不足で機械の故障が相次いだ。100台以上の機械のチェックなどを5~6人で担当する過酷な作業だったが、「『日本は必ず勝つ』と信じて、ひたすら仕事に打ち込んだ」と振り返る。8月15日。寮の一室に集められ、玉音放送を聞いた。涙がこぼれた。
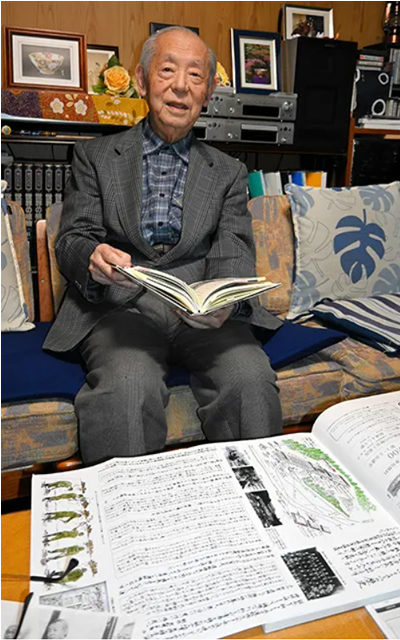
「戦争は周りを見えなくする」と小山田さん。鉱山もまた、時局や戦争に翻弄(ほんろう)された場所だった。
閉山から半世紀以上がたつ手稲鉱山だが、今も稼働している施設がある。坑内から出る鉱物成分を含んだ水を石灰で中和する処理施設で、三菱マテリアルの関連会社が24時間、施設を管理する。
手稲区在住の林俊一さん(76)は67歳までの7年間、この施設の所長を務めた。近年、海外の事業者が日本の鉱物資源に目を向けていることが気になっている。「一度掘ったら半永久的に水処理が続く。外国の会社がそこまで考えてくれるのか」と話す。
森の大切さも知った。「山の木々の保水力が高まれば、豪雨でもあふれ出すことはない」と説明する。
手稲鉱山で働く人たちの子どもが通うためにつくられた特別教授場が前身の手稲西小には、資料室「鉱山のへや」がある。

今でも鉱山があったほうがいい? 記者がたずねると、6年の武田詠斗さん(12)は答える。「にぎやかなのもいいかもしれないが、空気がおいしいのが一番」。6年の宮崎華さん(12)も「おばあちゃんやお母さんが山からウドやタラの芽を取ってきてくれる。そんな自然な豊富なところがうれしい」。鉱山のへやは、今の地域の良さを改めて教えてくれる場所でもある。
◇
連載<ディープに歩こう 札幌・手稲編>の7回目は、地域の郷土史研究家と記者がマチを歩き、手稲の歴史を紹介します。(佐藤元治)
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
手稲鉱山の歴史を詳しく教えてくださった、
北海道新聞社の佐藤元治記者に感謝いたします。
私が入学した手稲西小学校が、
軽川尋常小学校手稲鉱山特別教授場(1936年開設)だったとはじめてしりました。
軽川はがるがわと読みます。
私が子供の頃には、がるがわ牛乳がありました。
機会があれば
手稲西小学校の「鉱山のへや」に行ってみたいです。
“手稲鉱山の歴史”へのコメント
コメントをどうぞ







手稲鉱山があったという
ことは知っていました。
そのことの歴史は、
全く知りませんでした。
閉山したらそのままではなく、
管理しなくてはならないこと
があるのですね。
海外の事業者が日本の鉱物資源を
注目していることは、
新聞で目にしたことがあります。
記事をご紹介してくださって
ありがとうございます。
勉強になりました。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。札幌から小樽方面に車で向かうと手稲本町を過ぎたあたりから左側の山に手稲鉱山のあとが見えました。私が小さい頃には父親と光る石がある山に行けました。拾ってきた想い出があります。手稲鉱山から出る排水のため、自分が住んでいた裏に流れていた川には毒があると教えられ、川の水には触らないようにしていました。道新が詳しい記事を書いてくださりよくわかりました。手稲西小学校の資料室「鉱山のへや」にも行ってみたいです。
今日は大変な1日でした。
母の膝の福島先生の予約日でした。
昨日私が武井先生から処方してもらったトラムセットを母が誤飲し、ふらついて昨日倒れ、顔面にあざを作り車に乗せては吐き、レントゲンで立ち上がれば吐き、リハビリはしないで診察だけ受けてきました。福島先生はお優しいです。
私のところも吉野鉱山がありそこの子供は良い暮らしをしていました。
地名通り砂金が出ました。
歴史を知るのは面白いです。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。お母様、大変だったと思います。お大事になさってください。吉野鉱山のことは知りませんでした。手稲鉱山のこともよく知りませんでした。北海道新聞の記事でよくわかりました。私が小さい頃は札幌から手稲鉱山行きのバスを利用していました。父親が亡くなったのも手稲鉱山のイムスリハビリ病院です。
お疲れ様です。
今日は休ませて下さい。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
お大事になさってください。頭痛がよくなることをお祈りしています。