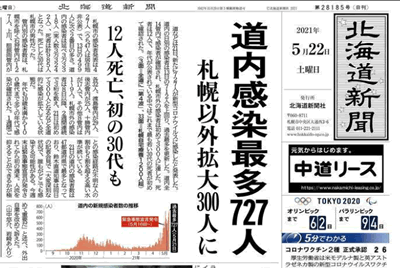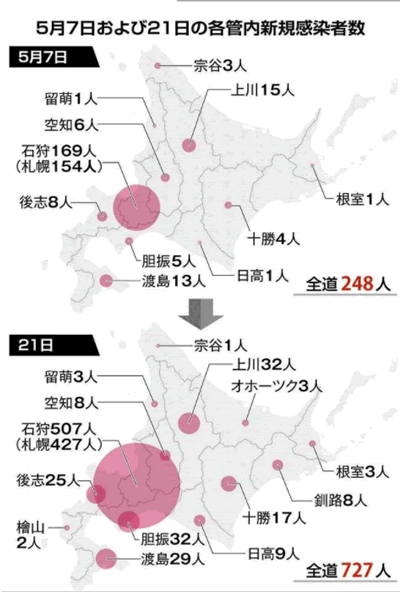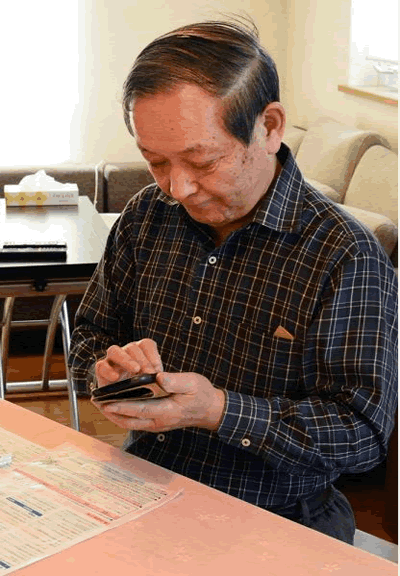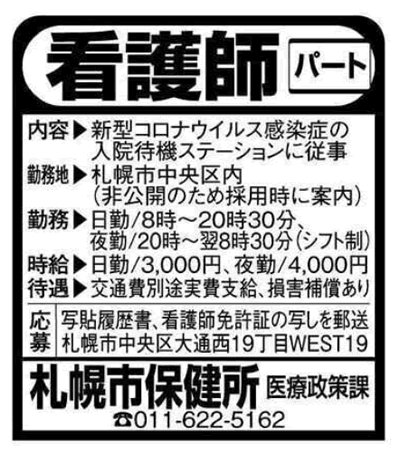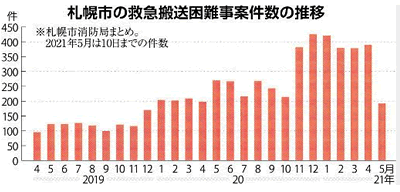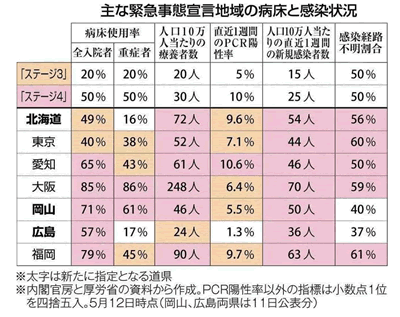医学講座
道内感染最多727人12人死亡
今日は2021年5月22日(土)です。
昨日の感染者数が北海道で過去最多になりました。
2021年5月22日、北海道新聞朝刊のトップ記事です。
道内感染最多727人 12人死亡、初の30代も
道などは21日、新たに727人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の日別の感染者は13日の712人を上回り、過去最多を更新した。道内全14管内で感染者が確認され、札幌市外の感染者は初めて300人に達した。死者は12人で、年代が公表されている中ではこれまで最も若い30代の死者が初めて確認された。
札幌市の感染者発表は427人(うち47人は居住地非公表)で、13日の499人に次ぐ2番目の多さ。道内の感染者は延べ3万3318人(実人数3万3242人)、死者は計985人となった。死亡した30代は札幌市の男性だった。
管内別の感染者数は、札幌市を除く石狩管内が127人、上川、胆振両管内が各32人、渡島管内が29人、後志管内が25人、十勝管内が17人で、その他8管内は1~9人。札幌市外の感染者は8日以降、2週間連続で3桁を数え、21日は初めて300人となるなど全道的に感染が拡大している状態だ。
年代も10歳未満から100歳代まで全ての年代で感染が確認された。1週間ごとの感染経路が不明な人の割合も5割を超える高い水準が続いている。
21日の道内の感染者数は47都道府県で最多となっており、鈴木直道知事は同日の記者会見で「大変深刻な状況で、誰もがどこでも感染する可能性がある。今週末は緊急事態宣言が発令されてから初の週末。人流を抑えることができるかが極めて重要だ」と述べ、外出自粛を改めて訴えた。(山中悠介、岩崎あんり)
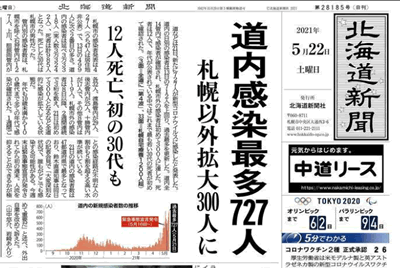
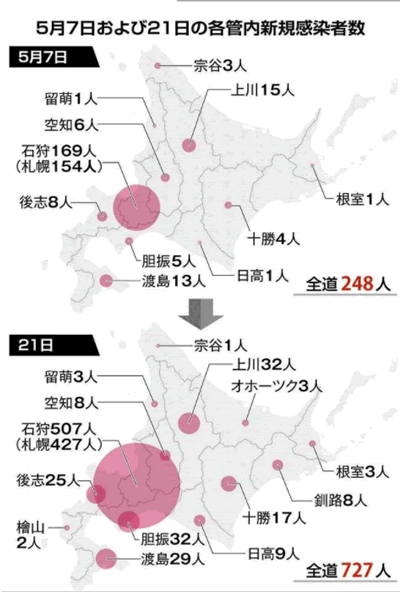
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
大変なことです。
北海道新聞の地図を見ると、
札幌の赤丸が大きくなっています。
鈴木直道知事が言われるように、
誰もが
どこでも
感染する可能性がある
…のです。
■ ■
第4波は感染力が強いのだと思います。
今まで以上に、
アルコール消毒をしっかりしましょう。
街中の消毒液には、
アルコール以外のものが入っているのもあります。
シュっとした時に、
アルコールの冷たい感じがしないものは要注意です。
何とか感染をコントロールしたいです。
今日も道内で5人死亡、658人が感染 札幌は409人でした。
医学講座
札幌の宿泊療養施設ホテルでクラスター
今日は2021年5月21日(金)です。
北海道の感染者数が過去最多となりました。
昨日のYahoo!ニュースです。
札幌市の新たな感染394人、死亡8人…宿泊療養施設のホテルでクラスター、8つの小中学校で学級閉鎖
5月20日、札幌市の新たな新型コロナウイルス感染確認は394人でした。8人が亡くなっています。
394人は、13日の499人に次いで過去2番目に多い感染確認です。新たなクラスターが4つ発生しました。257例目となるコロナ患者用の宿泊療養施設として運用されている南区川沿の「アパホテル&リゾート札幌」で、札幌市の職員2人を含む施設の運営業務従事者10人、258例目となる老人福祉施設(名称非公表)で入所者4人、職員1人の合わせて5人、259例目となる白石区平和通の本通小学校で児童9人、260例目となる医療機関(名称非公表)で患者5人、職員2人の合わせて7人の感染がそれぞれ確認されています。本通小学校は1クラスで学級閉鎖の措置がとられました。
さらに、クラスターにはなっていませんが、小中学校での感染も止まりません。中央区の幌南小学校で児童1人、東区の札苗緑小学校で児童1人、東区の栄南中学校で生徒1人、白石区の北白石中学校で生徒1人、西区の琴似中学校で生徒1人、手稲区の前田北中学校で生徒1人、白石区の北都中学校で生徒2人の感染がそれぞれ確認され、学級閉鎖などの措置がとられました。
札幌市(死亡)/北海道全体の感染確認
<5月>
・1日(土) 131人(1人)/180人
・2日(日) 244人(5人)/324人 初の200人超
・3日(月) 88人(4人)/114人
・4日(火) 201人(4人)/233人
・5日(水) 126人(1人)/179人
※札幌市内「まん延防止」適用を国に要請
・6日(木) 251人(3人)/320人
・7日(金) 154人(4人)/248人
・8日(土) 277人(3人)/403人
・9日(日) 326人(7人)/505人 初の300人超
※札幌市内「まん延防止」適用
・10日(月) 266人(4人)/409人
・11日(火) 279人(5人)/420人
・12日(水) 352人(6人)/529人 初の350人超
・13日(木) 499人(5人)/712人 感染最多 初の400人超
・14日(金) 346人(6人)/593人
※「緊急事態宣言」決定
・15日(土) 344人(1人)/565人
・16日(日) 322人(4人)/491人
※「緊急事態宣言」発出
・17日(月) 210人(7人)/372人
・18日(火) 377人(7人)/532人
・19日(水) 381人(11人)/603人 死亡最多
・20日(木) 394人(8人)/681人
・21日(金) 427人(12人)/727人(過去最多)
5月20日(木)午後4時00分配信
(以上、Yahoo!ニュース、北海道放送(株)より引用)
■ ■
アパホテル&リゾート札幌は大きなホテルです。
日本マイクロサージャリー学会が開催されたこともありました。
感染された方にお見舞い申し上げます。
札幌市の職員2人を含む
施設の運営業務従事者10人の方たちが、
ワクチンを打ってもらっていたかわかりません。
救急隊やコロナ患者さんの業務に就く方には、
最優先でワクチンを打っていただきたいです。
感染しないように気をつけます。
医学講座
ワクチン接種予約300回空振り
今日は2021年5月20日です。
札幌は晴れのいいお天気でした。
昨日からはじまった75歳以上のワクチン予約が、
うまくできないようです。
2021年5月20日、北海道新聞朝刊の記事です。
札幌ワクチン接種予約 「先着順」に高齢者困惑 300回空振り 病院業務に支障も
新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、札幌市で一般高齢者向けの予約が始まった19日、集団接種向けの専用電話とインターネットの受け付けには申し込みが殺到し、予約できなかった高齢者は「一日中、電話したのに」と肩を落とした。個別接種を行う市内の「かかりつけ医」にも電話が相次ぐなどして業務に影響が出た医療機関もあった。市は「希望者は全員接種できるので、焦らずに」と呼び掛けているが、先着順の予約制度が混乱を招いているとの批判もあった。
「電話がパンクする予感はあったが、こんなにつながらないとは」。札幌市北区でペットショップを経営する小泉詔信さん(78)は疲れた声で話した。
午前9時の受け付け開始から約1時間、集団接種向けの番号に65回ほど電話したが、全くつながらず断念。ネットも試したが、開始40分でこの日の予約は終了していた。結局、一度もつながらないまま午後6時の受付終了時間となり、「感染したら重症化する不安もあり、できるだけ早く打ちたかったのに」と嘆いた。
札幌市が今回の接種対象としたのは、75歳以上の約27万人。かかりつけ医での個別接種を基本とし、それが難しい場合は市内2カ所での集団接種になる。市は19日、集団接種の電話予約枠約8千人分を用意したが実際の受け付けは約5千人にとどまった。ただ、同市は「スタッフ125人で対応し、予約1件に平均15分とすれば9時間で最大約4500件」としており、19日の予約件数は想定を上回ったとみる。
ただ、同市東区の会社社長、北川一夫さん(75)も集団接種の専用番号と、かかりつけ医の両方に電話したが予約できなかった。接種券と一緒に届いた医療機関リストを見て、近くの病院などに正午まで計300回は電話を鳴らしたが大半は話し中。ようやくつながった病院の予約はすでに埋まっていた。「電話する方も受ける方も大変。年齢などを基準に市が接種の順番を決めてくれた方がよかった」と話した。
東区役所などでは午前9時以降、しびれを切らした高齢者が窓口を訪れて「何とかならないのか」と詰め寄る場面も。ただ職員側は「電話をかけ続けて」と繰り返すしかなく、東区の無職男性(75)は「電話もネットもつながらず、役所に来てもどうにもならない」といら立っていた。
一方、予約を受けるかかりつけ医も混乱した。北区の民間病院では午前9時10分には来週分の予約は埋まってしまったが、夕方まで電話が鳴りやまず、直接来院する高齢者も多かった。看護師は「朝からずっとこの状態。ワクチンの問い合わせだけで電話が埋まり業務に支障が出ている」とうんざりした表情で話した。
一部の医療機関では、事前予約を受け付ける「フライング」もあったようだ。同市清田区の無職高田聡子さん(80)は19日、かかりつけの内科医院に電話したところ、「数日前から予約を受け付け、すでに数十人が予約した。きょう予約しても、いつ接種できるかは分からない」と言われたという。高田さんは「こんなことが起きるとは想像もできなかった。あまりにずさんな制度だと思う」と憤った。(阿部里子、加藤祐輔、石垣総静)
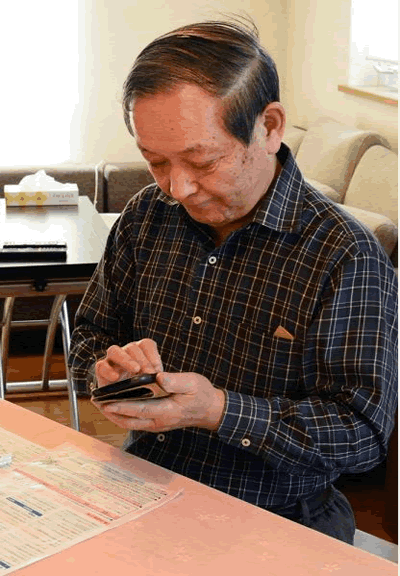
受付開始時間の午前9時からワクチン接種の予約電話をかけ続ける小泉詔信さん。結局、この日は一度も電話はつながらなかった=19日、札幌市北区
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
札幌市は75歳以上の対象者が約27万人だそうです。
これを2ヶ所の接種センターで注射するのですから、
無理なんです。
開業医も診療の片手間ではできません。
東京の大規模接種センターは、
自衛隊から業務委託を受けた企業が看護師の手配をしています。
時給2100円~のようです。
■ ■
医師の求人情報をネットで見ると、
東京で一日10万円~12万円。
札幌で一日8万円らしいです。
看護師さんは札幌市保健所の求人より応募しやすくしています。
東京の大規模接種センターで注射する看護師さんは、
LINEで勤務希望日を送るシステムのようです。
一般の人にもワクチン接種を拡大するためには、
今のやり方のままではダメです。
医学講座
札幌の接種予約受付開始
今日は2021年5月19日(水)です。
札幌は晴れのいいお天気です。
ライラックが満開です。
街中は緊急事態宣言です。
飲食店は臨時休業で、
デパートも週末は化粧品と食料品以外は営業しません。
大変なことになっています。
■ ■
今日から札幌の高齢者(75歳以上)の接種予約受付がはじまります。
かかりつけ医がいない人には、
大規模接種会場が2ヵ所あります。
うちのばあさんは、
医療法人がつくったサ高住に住んでいますが、
残念なことに、
開設した医療法人ではワクチンを打ってもらえません。
ばあさんは医療法人の病院にかかっています。
これが現実です。
■ ■
2021年5月19日、北海道新聞朝刊の記事です。
「かかりつけ医」ない人向けの集団接種会場 札幌市が公開
札幌市が24日から開始する新型コロナウイルスワクチンの一般高齢者向け接種で、市は18日、市内2カ所に開設する集団接種会場を報道陣に公開した。市は受診歴のある「かかりつけ医」での接種を基本とするが、市内の医療機関には19日の予約受け付け前から問い合わせが相次ぎ、混乱も生じている。集団接種に希望が集中する可能性もあり、市は感染対策に気をもむ。
集団接種会場は、札幌エルプラザ(北区)と札幌パークホテル(中央区)の2カ所。公開されたパークホテルでは、地下の多目的ホール約2300平方メートルに予診、接種のブースや接種後の待機所などを設けた。市民が迷わず移動できるよう大きな案内板を各所に設定し、常時自動で換気する。
24日からの接種は当面、75歳以上の約27万人が対象。集団接種会場の2カ所では、1日当たり計約2千人の接種を予定し、パークホテルは約1700人を受け入れる。医療従事者40人が常駐し、来場者が密集しないよう誘導スタッフ約100人も配置する。
75歳以上の予約受け付けは19日からだが、既に接種券を受け取った人から医療機関に多数の問い合わせが寄せられている。市内の接種は医療機関約480カ所での個別接種が基本で集団接種はかかりつけ医がない人向け。ただ「かかりつけ」の基準が医療機関で異なるため、希望する医療機関の予約が取れないなどの事情で集団接種を選択する人が増える可能性も。市ワクチン接種担当部は「来場した市民が滞留しないよう注視する」としている。
集団接種は専用電話(午前9時~午後6時)とインターネットで受け付ける。
市内では、集団接種会場とは別に、道と国が6月下旬以降をめどに道民対象の大規模接種会場の設置を検討している。(阿部里子)

札幌市が札幌パークホテルに設けた集団接種会場。ワクチン接種後の経過観察を行う待機場所には間隔を十分に取っていすを並べるなど感染対策に配慮していた=18日午前9時15分、札幌パークホテル
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
うちのばあさんは、
病院と連携、安心サービス
…とHPに書いてあるサ高住に住んでいますが、
残念なことにお隣にある病院では、
ワクチンを打ってもらえません。
自分で見つけてワクチンを打ってもらいます。
息子の私は不満です。
かかりつけ医があってもワクチンを打ってもらえない人が、
たくさんいると思います。
■ ■
これから高齢者以外の人にもワクチン接種をしなくてはなりません。
私は大規模接種会場を増やすとか、
企業の定期健康診断でワクチン接種をするとか、
大学や学校の健康診断でワクチン接種をするとか、
医療機関に頼らない方法で、
ワクチン接種をすすめるのがいいと思います。
そうしないと全国民にワクチン接種は無理です。
早く米国のようにマスクなし生活になりたいです。
医学講座
札幌に大規模接種会場
今日は2021年5月18日(火)です。
北海道新聞朝刊のトップ記事です。
札幌に大規模接種会場 道が設置検討 6月下旬以降
高齢者向けの新型コロナウイルスワクチンに関し、道は国と連携し、札幌市内に大規模接種会場を設置することを検討している。道民であれば居住地にかかわらず接種が受けられる広域センターとし、国は「打ち手」となる医師や看護師の確保を支援する。開設は6月下旬以降とみられ、道内自治体の接種状況をみて、札幌以外での設置も検討する。
■国と連携、居住地限定せず
政府は65歳以上の高齢者へのワクチン接種を7月末までに終える目標を掲げる。だが、道内では札幌市などの大規模自治体が7月中の完了は困難とし、国に支援を要請。道も国に都市部への大規模接種会場設置などを要望していた。
政府は24日、東京と大阪に直轄の大規模接種センターを開設し、自衛隊の医師らが接種を担う。一方、札幌では自衛隊は関与せず、国と道、札幌市が連携して運営。国が国立大などに協力を呼び掛け、医療従事者の確保を支援する。開設場所や受付可能件数は未定で、体育館やイベントスペースなどを活用する方向で検討している。
高齢者向けのワクチン接種は市町村が担うことを基本とし、大規模会場は接種が遅れる市町村を補完する位置付けで、国は地方自治体との連携の全国モデルとしたい考え。
札幌以外の大規模接種会場については、札幌会場や道内市町村の接種状況などを踏まえ、中核市で検討する。(岩崎あんり)

(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
私はいい考えだと思います。
札幌市内で高齢者ワクチン接種を引き受けた医療機関は、
ふつうの診療ができないほど問い合わせがあるようです。
電話がつながらないところもあり、
診療に支障が出ているようです。
私は大規模接種センターに賛成です
■ ■
ワクチン接種が進まない原因は、
ワクチン接種の費用一回2070円
この低価格です。
2070円が税込か非課税かわかりません、
この価格を決めたのが、
厚生労働省健康局健康課予防接種室です。
医療現場のことを考えていません。
どうがんばっても赤字になります。
■ ■
ワクチン接種で大変なのは、
注射そのものではありません。
たくさんの人が来て、
受付をして、
問診を確認して、
ワクチンを注射器に詰めて準備するのが大変です。
広い会場でなければ密になります。
換気がよいところでなければできません。
私は緊急事態宣言が出ている都市は、
国の責任で大規模接種センターをつくるのがいいと思います。
選挙の投票会場でワクチン接種もして、
医学部6年生にも打たせてください。
医学講座
札幌市保健所_パート看護師募集
今日は2021年5月17日(月)です。
札幌で新型コロナ変異株の感染者数が急増しています。
今朝の北海道新聞に、
札幌市保健所の看護師募集広告が載っていました。
保健所も人手不足で困っています。
PCR検査で陽性になった人が、
入院を待つ間、
待期ステーションに勤務する看護師さんです。
■ ■
日勤で時給3000円は、
札幌市の非常勤職員としては破格です。
医師の給与でもいいくらいです。
それだけなり手がいないのだと思います。
保健所でも人材募集は、
派遣会社に依頼しないと集まりません。
交通費別途実費支給、
損害補償ありと書いてあります。
■ ■
もし新型コロナに感染したら、
損害補償をしてくれるのかなぁ~?
…と思います。
日勤:8時~20時30分
夜勤:20時~翌8時30分
これはきついです。
拘束時間が12時間以上になります。
途中、休憩時間があったとしても、
患者さんからコールがあると休めません。
応募してくださる看護師さんがいるといいなぁ~
…と陰ながら保健所を応援しています。
■ ■
看護師パート
内容▶新型コロナウイルス感染症の入院待機ステーションに従事
勤務地▶札幌市中央区内
(非公開のため採用時に案内)
勤務▶日勤/8時~20時30分、
夜勤/20時~翌8時30分(シフト制)
時給▶日勤/3,000円、夜勤/4,000円
待遇▶交通費別途実費支給、損害補償あり
応募▶写貼履歴書、看護師免許証の写しを郵送
札幌市中央区大通西19丁目WEST19
札幌市保健所 医療政策課
☎011-622-5162
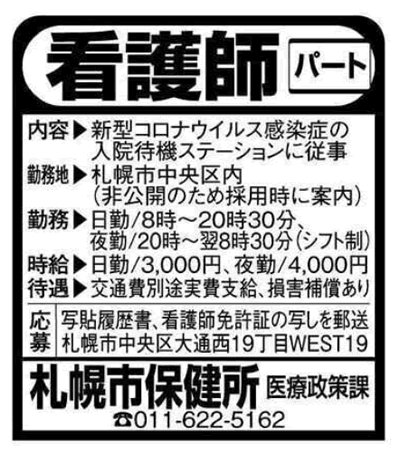
医学講座
札幌の急患を帯広へ搬送
今日は2021年5月16日(日)です。
札幌で変異型の感染が急増しています。
今日の北海道新聞電子版の記事です。
急患の搬送困難急増 病床逼迫の札幌市 コロナ前の4倍、帯広へ移送も
新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、札幌市内で患者の搬送先がすぐに決まらない「救急搬送困難事案」が増加している。市消防局によると、4月は前年同月比191件増の389件で、コロナ禍前の4倍に急増。5月も前年を上回るペースで増えており、コロナの疑いがある患者が市内では病床が見つからず、帯広市や留萌市まで搬送されるケースも出始めた。関係者は「感染がさらに広がれば、コロナ以外の救急搬送体制も維持できなくなる」と危機感を募らせている。
「毎日のように患者の受け入れを断られる。救急医療の現場が崩壊しかねない状況だ」。札幌市消防局の救急隊員は、現状をこう説明した。隊員たちは発熱やせきなどの症状がある急患の場合、コロナの疑いもあるとみて、防護服を着用。救急車から電話をかけ、患者の症状に応じた受け入れ先を探すが、医療機関への照会が4回以上にわたり、現場到着から搬送開始まで30分以上かかる「救急搬送困難事案」が続発している。
背景にあるのは、コロナ患者の急増に伴う市内の病床逼迫(ひっぱく)だ。院内感染を警戒し、コロナ疑いのある急患は受け入れを断る医療機関も多く、症状が軽い患者は救急車の中で観察後、本人の同意を得た上で搬送しない例も増えているという。
市消防局によると、2019年度の救急搬送困難事案は1706件だったが、コロナ禍が起きた2020年度は3660件に倍増。特に道内が感染「第3波」に見舞われた昨年11月以降は毎月300件を超える状況が続く。今年4月の389件のうち、コロナの疑いがある急患は122件だった。5月は10日までで既に192件に達しており、月別では過去最多となる可能性がある。
医療機関側の負担感も増している。救命救急センターのある道内の基幹病院の一つ、手稲渓仁会病院(札幌市手稲区)は今月4日、64件の急患の受け入れ要請があったが、病床の確保が難しいなどの理由で28件を断念した。コロナ疑いで受け入れた患者の中には20カ所以上の医療機関に断られた末、同病院に搬送された人もいたという。勤医協中央病院(同市東区)の担当者も「コロナ患者が急増した5月以降、10回以上受け入れを断られた急患が来るケースが増えた」と話した。
札幌市外への搬送も相次ぐ。市保健所によると、コロナ疑いのある人を含めた急患の市外搬送は3月には1件だけだったが、4月は17件まで増加。5月は13日現在で19件に達している。小樽市や江別市などの札幌近郊では搬送先が見つからないことも増えており、手稲渓仁会病院の奈良理救命救急センター長は「地方の患者が札幌に搬送されるという通常の医療体制が逆転している。このまま地方でもコロナの感染が拡大すれば、札幌の患者は行き場を失う」と危惧する。(広田まさの、山村麻衣子、菅沢由佳子)

札幌市内を走る救急車。新型コロナの感染拡大の影響で、搬送先を探す救急隊員の負担も増している=14日
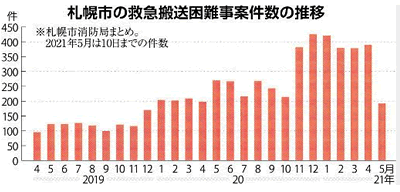
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
この記事を読んで驚きました。
私は高度救命救急センターがある札幌医大病院、
市立札幌病院、
JA帯広厚生病院に勤務しました。
私の記憶する中で、
札幌の救急患者さんを帯広で引き受けたことはありませんでした。
■ ■
逆にJA帯広厚生病院に勤務していた時に、
帯広では治せない患者さんを、
市立札幌病院にお願いしたことがありました。
その時は天候の関係でヘリが使えず、
自衛隊機に患者さんの搬送をお願いしました。
札幌の患者さんを帯広に搬送するのは大変です。
私はワクチン接種に期待しています。
コロナ禍を何とかしたいです。
医学講座
北海道緊急事態宣言2021
今日は2021年5月15日(土)です。
札幌は晴れのいいお天気で、
ライラックが咲いています。
八重桜も、
チューリップも満開です。
ところが新型コロナ変異株が増えています。
北海道も緊急事態宣言です。
■ ■
2021年5月15日、北海道新聞朝刊の記事です。
緊急事態の解除、厳しい道のり 道内ほぼ変異株に 昼の人出減も不可欠
緊急事態宣言の発令が決まった北海道では、ほぼ全てが感染力の強い変異株に置き換わっており、解除までには厳しい道のりとなるのは必至だ。専門家の中で解除の条件にすべきとの意見が強まる「ステージ2」に至るまで、現在のほぼ半数の新規感染者数だった「第3波」でもピーク時から2カ月かかった経緯もある。昼間も含めて人出を減らすなど、徹底した感染対策が求められそうだ。
「従来の対策では長い時間をかけなければ、感染者数は減っていかない」。国立感染症研究所(感染研)の鈴木基(もとい)・感染症疫学センター長は「人の接触機会を減らすあらゆる手段を講じるしかない」と強調する。
感染研はウイルスは「N501Y」という変異を持つ英国型の変異株に、道内では、ほぼ100%、全国では90%以上が置き換わったと推定。英国株は従来株に比べ、感染力が1.3倍、重症化リスクも1.4倍となる可能性があるという。感染力の強さや免疫への影響が指摘されるインド株の流入も懸念される。
変異株の猛威を受け、政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長は解除の条件について「(新規感染者数などが)下げ止まってすぐ解除するとリバウンドが来る。2、3週間は我慢することが時間稼ぎになる」と主張。「ステージ3にとどまらず、2相当が望ましい」と指摘する専門家が増えている。
新規感染者のステージ2の値は直近1週間で人口10万人当たり15人未満。東京、大阪では第3波の感染ピーク時からステージ2相当に至るまでそれぞれ44日、28日を要した。
感染研の脇田隆字所長は両都市とも現状からステージ2に減少させるには、少なくとも同程度の期間が必要とみる。
第3波で北海道は昨年11月中旬に10万人当たり約31人とピークに達し、ステージ2相当に下がったのは今年1月末。現在は新規感染者数は50人を超え、ステージ4に達する指標も多い。宣言による対策が先行する東京や大阪でも解除まで相当の時間がかかることを考慮すれば、解除に向けた「出口」は見通せていない状況だ。
釜萢敏(かまやちさとし)・日本医師会常任理事は、取るべき対策として外出制限や店舗の昼の営業自粛などを挙げ「道民には不便をかけるが、今優先すべきは感染拡大の防止だ」と話す。(小森美香、立野理彦)
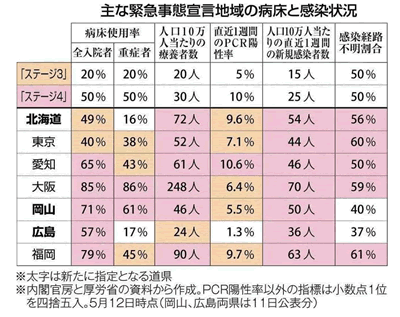

(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
ワクチン接種はなかなかすすまない。
変異株で医療崩壊。
困りました。
今まで以上にしっかりと消毒、手洗い、マスクをして、
とにかく感染しないことです。
若い人がどこで感染したかわからない、、、
…というのが感染者数増加の原因のようです。
緊急事態宣言も仕方がないと思います。
医学講座
選挙の投票日にワクチン接種を
今日は2021年5月14日(金)です。
札幌は晴れのいいお天気です。
八重桜とチューリップが満開です。
お花はきれいですが、
世の中は深刻です。
新型コロナの感染者数が増えています。
何とかワクチン接種を早くしなくては、
感染をコントロールできません。
■ ■
高齢者のワクチン接種予約がはじまりましたが、
なかなか予約が取れません。
全国民にワクチン接種となると、
いつのことやら?
…と不安になります。
国民の大部分に、
大規模なワクチン接種をしたことがありません。
国にも自治体にもノウハウがありません。
■ ■
ワクチン接種で大変なのは、
注射ではありません。
問診で持病やアレルギーを聞いたり、
注射器にワクチンを吸って準備するのが大変です。
ワクチン接種後に具合が悪くなった人を、
しっかりサポートするのも大変です。
短期間にワクチン接種を完了するには、
今までの方法ではできません。
■ ■
私は今年任期満了を迎える、
衆議院議員選挙の日に、
投票会場でワクチン接種をするのがいいと思います。
もちろん不在者投票でもワクチン接種をします。
今から準備すれば、
秋までには何とかなると思います。
ワクチンが準備できなかったら、
年齢によって接種する人を分けるのがいいです。
■ ■
選挙会場では本人確認ができます。
自治体の人がたくさん来ているので、
自治体職員にも問診をしてもらいます。
予診票を書いてきてもらって、
チェックするだけなら資格がなくてもできます。
問題がある人だけを、
有資格者の看護師や保健師がします。
■ ■
ワクチンの準備は、
薬剤師や臨床検査技師がします。
微量の薬液を注射器に吸って準備するのは、
医師よりも臨床検査技師が上手だと(私は)思います。
注射は看護師がします。
一つの投票会場にある程度の看護師がいればできます。
医師は2人で交代しながらします。
私でよければ投票所に手伝いに行きます。
こんなことでもしなければ、
遅れている日本のワクチン接種は進みません。
投票所でワクチン接種をすると、
過去最高の投票率になります。
医学講座
看護師すり減る心
今日は2021年5月13日(木)です。
昨日の看護の日2021
…の続きです。
今朝の北海道新聞に掲載されていた、
札幌の看護師さんのお話しです。
ほんとうに大変だと思います。
■ ■
看護師すり減る心 病室内15分に制限 「孤独な最期 胸痛い」
道内の新型コロナウイルスの新規感染者が最多を更新する中、看護師が心をすり減らしながら医療現場を支え続けている。現在の感染「第4波」では1日の感染者が500人を超え、重症患者も急増。感染者の7割近くが集中する札幌市では患者の家族のみならず、看護師も長時間寄り添うことが難しくなり、従来の「みとり」ができないケースが増えている。「何ができるのかと悩み、無力な自分に憤りを感じる」。看護師らは葛藤を繰り返し、今も病棟に立つ。(田鍋里奈、内山岳志)
「苦痛と不安の中、一人きりで過ごし、亡くなっていく患者を見るのは本当に悲しい」。新型コロナの軽症・中等症患者を受け入れるKKR札幌医療センター(札幌)でコロナ病棟の看護主任を務める沓沢希世美さん(45)はこう吐露した。
■退院の姿が支え
センターがコロナ患者を受け入れ始めた昨年2月、専用病棟の担当になった。防護服を着て6時間近く看護し、汗だくになった。マスクとフェースガードを外しての食事は一人きりで、同僚と雑談もできない。それでも回復し、退院する患者の姿が心の支えだった。
しかし、変異株が本格的に拡大するなどした「第4波」では札幌市内の病床が逼迫ひっぱく。センターも専用病棟の20床は常に満床となり、退院が決まった患者のベッドには、すぐ次の患者が到着する。院内は「ぎりぎりの状態」に追い込まれた。
■親族から苦情も
重症化した患者の中には人工呼吸器の装着などの延命治療を選択せず、センターで最期を迎える人が増え始めた。終末期の患者には家族や看護師が寄り添い、手を握ってみとってきたが、今は感染対策で家族は面会できず、看護師も15分で病室を出なければならない。「一人きりで残された患者は、どんな思いだろうか。考えたら胸が痛くなる」。沓沢さんは漏らす。
「最期なのに顔も見られないのか」と親族から苦情を言われたこともあった。気持ちは痛いほどわかるが、神経はすり減っていく。
大型連休中も普段通り、週5日勤務した。人出が増えたというニュースを見るたびに「医療現場の状況が伝わっていない」と思う。コロナ禍が1年以上に及び、外出したい人の気持ちも分かる。ただ、目の前で誰にも手を握られずに亡くなる人たちがいる。「そんな悲しい現場を見るたびに、やるせない気持ちになる」
■56%が変調訴え
北海道医療センター(札幌)など国立病院機構の労働組合が今年2月、全国の看護師約2400人に行った調査では、コロナ病棟で働く看護師の56%が「心身に変調がある」と答えた。退職を考えたことがあるとの回答も51%に達した。
5月12日は看護師の社会貢献をたたえる「看護の日」。コロナ患者と向き合う札幌の30代の女性看護師は「世間と医療現場の間には溝がある」と言った。第4波では20~30代が重症化するケースが増えているが、まん延防止等重点措置が適用されても人出が減ったとは思えない。「帰省や外食はできず、唯一のストレス発散は好きなカフェでのテークアウト。私たちはいつまで頑張ればいいのか」

防護服に身を包み、業務にあたるコロナ病棟の看護師=12日午後4時40分、KKR札幌医療センター提供
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
コロナ病棟で働く看護師の56%が「心身に変調がある」
これは大変なことです。
帰省や外食ができないのもつらいです。
連休中も普段通り週5日勤務
お疲れになっていると思います。
苦痛と不安の中、
一人きりで過ごし、
亡くなっていく患者を見るのは本当に悲しい
■ ■
もし私が入院しても、、、
家族は面会に来れないですし、
その分だけ看護師さんに負担をかけます。
早く多くの人にワクチンを接種して、
米国のようになりたいです。
何かいい方法がないか?
考えてみたいと思います。