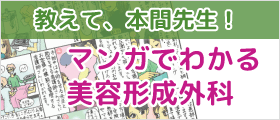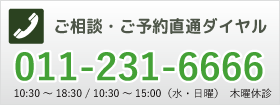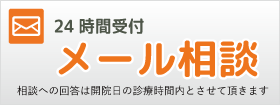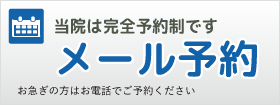医学講座
山崎浩一先生を偲ぶ
平成20年2月6日、北海道新聞朝刊の記事です。
がんと闘った専門医・山崎さんがのこした言葉
1%の希望 信じよう
患者、最後まで支え続ける
■ ■
北大大学院医学研究科で中皮腫や肺がんを専門としてきた医師(46)が1月12日、自ら専門とする中皮腫で他界した。
治療者と患者、二つの立場を経験した医師がのこした言葉は「1%の希望」。
死に直面して発せられた希望という言葉は、のこされた人に何を伝えようとしたのか。(佐藤千歳)
■ ■
呼吸器内科学分野(第一内科)准教授、山崎浩一さん。
2006年6月、職場の健康診断で肺に影が見つかる。
すぐ精密検査。悪性胸膜中皮腫と診断された。
当時44歳。肺の悪性腫瘍の専門家として活躍していた。
検査結果を知ったのも、米国の学会から札幌に戻った日のこと。
「こんなに元気なのに。信じられない」。
息切れしないか、階段を一段おきに駆け上がってみた。
「いつもと変わりないんだよ」-。妻の望美さん(44)に語りかけた。
■ ■
6月末、左肺胸膜全摘出の手術を受ける。
経過は順調だったが、9月、骨転移を含む全身性の転移が見つかった。
衝撃はより大きかった。
「転移して、抗がん剤が効く確率は30%。効かなければ余命三ヵ月だ」。
望美さんに説明した。
◆命燃やし診察
「責任感が強く、他人に厳しく、自分に最も厳しい人」。
十年の間、一緒に仕事をしてきた第一内科の大泉聡史助教(41)は言う。
仕事を離れれば、スポーツ好きの親しみやすい先輩だった。
■ ■
北大の学生時代、山崎さんはテニス同好会にいた。
ダブルスを組む友人が、強豪との対戦前、「勝つのは無理だ」と山崎さんに言ったことがある。
「勝つ可能性が1%なら、練習で5%にできる。
そこでうまく作戦を立てれば、10%にできる。
10%なら、10回試合をやれば一回は勝てるってことなんだぜ。
その一回が本番の試合かもしれないじゃないか」
■ ■
真剣に怒る山崎さんの表情を、友人は忘れられない。
二人は勝った。
友人の思い出は、山崎さんの闘病の姿勢と重なる。
「30%も可能性がある。良い面を見ていこう」。
そう言って始めた再発後の抗がん剤治療は、効果を現した。
■ ■
このころ、病棟と外来の仕事はやめていた。
だが、症状が落ち着くと、他の病院にかかる患者が専門家の意見を求めるセカンドオピニオン外来で、肺がんや中皮腫を担当し始めた。
「患者さんより山崎君の方がつらそうに見えました。
それでも『患者さんに説明したい』と。
やり続けたい仕事だったのでしょう」。
第一内科の西村正治教授は言う。
■ ■
第一内科の山谷敦子副看護師長(42)は、
「患者さんの性格や職業、家族まで考えて治療方針を決める先生だった」。
自らもがん患者となり、患者の立場を思いやる言葉は確実に増えた。
◆確率との戦い
昨年9月26日。
医局講演会で、山崎さんが講師を務めた。
後輩の医師に、息切れを押さえながら、語りかけた。
「がん患者に向き合う医師は、病気の進行について悲観的な見通しを言うのは絶対にやめてほしい。
患者さんに希望を与えよう。
そのためには、がん患者を治した経験をたくさん持ってほしい」
患者として得た経験を医療現場に伝えようと、懸命だった。
■ ■
現代のがん治療は、確率との戦いでもある。
抗がん剤が効く確率、放射線治療が効く確率、五年生存率、余命-。
それぞれの選択肢の持つ確率が、治療方針を決める鍵となる。
悪性中皮腫は進行が早い。
「骨転移があれば、過去の症例から、多くの医者は『もうだめだ』と思ってしまう。
転移しても五年、十年と生きる人がいるが、可能性はかなり低い」 (西村教授)
■ ■
治療の効果が出る確率が低ければ、積極治療を中止し、
苦痛を取り除くことに重点を置くターミナルケアに移行する選択肢がある。
「もういいですよ」。
そう言って穏やかな末期を望む患者もいる。
緩和ケア病棟やホスピスが増えた現在、尊重されるべき選択肢だ。
ただ―。わずかな可能性にかける患者がいる。
山崎さんはその一人だった。
■ ■
主治医の大泉さんや、北大放射線科の白土博樹教授と相談しながら、
抗がん剤や放射線の治療を続けた。
病室にパソコンを持ち込み、仕事もやめなかった。
「サッカーの試合なら、残り一分、0対4の状況でも、がんばる患者さんがいる。
その気持ちを、最後のホイッスルが鳴るまで支えるのが医師の役目だと。
私たちが普段忘れがちなことを、山崎先生に教わった」。
白土教授は言う。
■ ■
そして、昨年12月。山崎さんはホイッスルが間近いことを覚悟する。
「エンドステージだ」。
望美さんに言った。
専門医として、自らの病状を冷静に見極めていた。
まるで、学会の手配をするように、自分の葬儀の用意を始めた。
◆最後の元旦に
2008年、元旦。
外泊した自宅のソファで、
山崎さんはノートパソコンをひざに抱き、
葬儀で朗読してもらう「病状報告」を少しずつ打ち始める。
■ ■
「本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございました…」
翌日は、テレビ中継の箱根駅伝を、じっと見ていた。
山崎さんは、スポーツが好きなわけを、望美さんに話している。
「スポーツは、何があるか分からないよね。
終わりの方に大逆転のドラマがあるかもしれない。それが楽しいんだ」
12日早朝、山崎さんは北大病院で永眠した。
◆「心構え」託す
18日、がん治療の医師や看護師を集めた研究会で、
白土教授が「病状報告」にあった山崎さんの言葉を紹介した。
今日は治らなくても、明日はよい治療法が見つかるかもしれない。
1%の希望があれば、闘病意欲のある患者さんには、
その1%にかけてがんばろうと言うべきだ-。
■ ■
命の終わりを見つめながら、
前を向いて生きること、
その闘いを支える医療関係者の心構え。
山崎さんのメッセージは、静かに波紋を広げている。
■ ■
中皮腫
胸膜や腹膜などの表面を覆う中皮細胞から発生する悪性腫瘍(しゅよう)のこと。
アスベストが関与していることが多く、
吸い込んでから30-50年後に発症するが、
吸引歴のない人が発症することもある。
胸腹中皮腫の場合、
胸水による呼吸困難や痛みを伴い、病気の進行は早い。
手術、放射線治療、抗がん剤治療が現在の標準的治療法。
■ ■
山崎さん自らが書いた「症状報告」
私は胸膜中皮腫という、アスベストの吸入歴のない比較的若い男性には非常にまれな病気になり、46歳という働き盛りの年齢で人生を終えることになりました。
私の専門は肺がん、胸膜中皮腫などの呼吸器腫瘍(しゅよう)の診断、治療であり、たくさんの胸膜中皮腫の患者さんを診てきました。
そのような私が自分の病状の経過がどうであったか、
自分が専門であった致死的疾患に罹患(りかん)したとき、病気にどう対応したかを、
本日お集まりのみなさまに正確にお伝えするのも一つの義務ではないかと考え、簡単な文章にまとめました。(中略)
私は、1年半以上の闘病の生活のほとんどを、まだ治る可能性があると信じて、自らの治療を勉強し、選択してきました。
この考え方は患者さんにとって非常に重要ではないかと思っています。
肺がんや胸膜中皮腫の患者さんの多くは、
最初の時点で医師から「もうあなたの病気は治りません」と宣告されていると思います。
しかし、1%でも0.5%でも治る可能性があると思えるかどうかは、治療を前向きに受けられるかどうかにつながる非常に重要な点であると私は思います。
最近では、現実的に5年も10年も長生きしている進行肺がんや胸膜中皮腫の患者さんが増えてきており、
そのような例をとって患者さんたちを励ましてあげることが重要ではないかと、治療する側と治療を受けた側の両方を経験した一人として強くそう思います。
(葬儀で大泉医師が朗読)
■ ■
山崎先生のご冥福をお祈り申し上げます。合掌。
北大第一内科HPにも、山崎先生のページがあります。

生前の山崎浩一さん。「熱い人だった」と周囲は口をそろえる
仏壇には、愛用の聴診器と腕時計の横に、
出身の札南高の甲子園出場を記念するボールが供えられた。
(北海道新聞より引用)