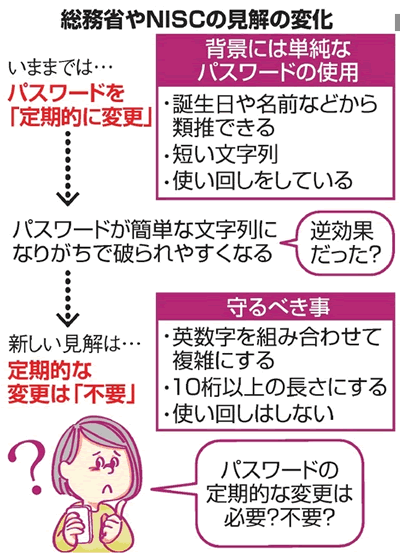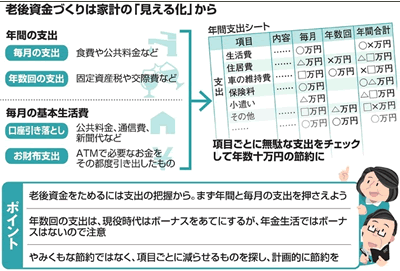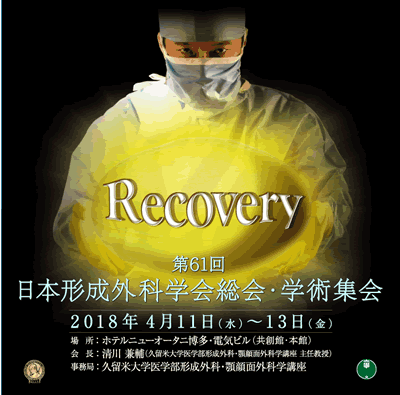医学講座
2018年5月と6月の予定ができました
移転先が迷走した札幌美容形成外科は、
南舘ビル(みなみだてビル)様のおかげで、
何とか2018年3月24日から、
〒060-0061
札幌市中央区南1条西4丁目16番地1南舘ビル4階
…で診療を開始しました。
ようやく院内も片付いてきて、
BGMもアロマも稼動しはじめました。
■ ■
毎年参加している日本形成外科学会にも行けました。
5月と6月には、
日本美容外科学会(JSAS)[東京]
日本熱傷学会[東京]
日本美容外科学会(JSAPS)[沖縄]
…に行きます。
学会以外は、
できるだけ土日の診療日を多くしました。
■ ■
明日2018年4月19日(木)にも残工事を行っていただきます。
わずか1ヵ月で完成したのですから、
多少の残工事は仕方がないです。
工事をしてくださった業者様には、
ほんとうに感謝しています。
63歳で多少くたびれていますが、
最新の知識を仕入れて、
がんばって診療を続けます。
2018年5月と6月の予定ができました。
HPでご確認ください。
医学講座
パスワード「定期変更は不要」
平成30年4月17日、朝日新聞朝刊の記事です。
パスワード「定期変更は不要」 国が方針一転「簡単な文字列になりがち」
パスワードは定期的に変更すべきか、変更しなくていいのか――。これまで国は定期的な変更を呼びかけてきたが、「変更は不要」との方針に変わった。大事な情報を守るパスワード。どう管理すればいいのだろうか。
■複雑に設定・使い回し避けて
セキュリティー対策を紹介する総務省の「国民のための情報セキュリティサイト」で3月、「定期的にパスワードを変更しましょう」という文言が削除された。日本のセキュリティー対策の司令塔である「内閣サイバーセキュリティセンター」(NISC)が、2016年末に定期的変更は不要と呼びかけたことを受け、総務省でも表記を改めたという。いまは「定期的な変更は不要」と記載されている。
総務省によると、ホームページで定期的変更を呼びかけ始めたのは03年から。利用者が単純なパスワードを使い回しがちで、一度パスワードが漏れると被害が一気に広がる恐れがあったためという。
NISCによると、パスワードの安全性を高めるには、英数字などを組み合わせて少なくとも10桁以上にする必要がある。担当者は「パスワードの変更を求めていくうちに簡単な文字列になりがちで、破られやすいものになる傾向が出てきた」と話す。「それよりは、複雑なパスワードを設定し、使い回しをしないことのほうが重要だと考えた」と説明する。
NISCが参考にしたのが、海外の動きだ。2010年、ノースカロライナ大学の研究チームが、定期的変更に関する研究結果を発表した。パスワードを90日ごとに変更する条件で学生らのアカウント約7700件を調べたところ、記号1文字を削除したり、「a」を「A」に置き換えたりするなど以前のパスワードから推測されやすい文字列に設定する傾向がみられたという。
セキュリティー業界の一つの指針になっている米国の国立標準技術研究所(NIST)も2017年、「ユーザーにパスワードの定期的変更は求めるべきではない」という趣旨のガイドラインを発表した。
こうした動きをセキュリティー対策が必要な金融業界はどう見ているのか。ネット銀行のソニー銀行(東京)の担当者は「国の方針は知っているが、従来の定期的変更を促すやり方を変えるつもりはありません」と話す。「万が一パスワードが漏れた場合を考えれば、定期的に変更するに越したことはない」と説明する。
慶応義塾大学の武田圭史教授(情報セキュリティー)によると、NISCが周知する「定期的な変更が不要」なのは、複雑なパスワードを設定し、かつ使い回しをしていないことが前提という。
米国のセキュリティー企業「スプラッシュデータ」が毎年発表する、実際に使われている危険なパスワードランキングによると、2017年の上位に「123456」「password」など簡単な文字列が並ぶ。武田教授は「守りたい情報を取捨選択し、重要なものなら複雑で長い文字列のパスワードを設定し、漏洩(ろうえい)対策として定期的に変更をするといいでしょう」とアドバイスする。(国吉美香)
■2017年の危険なパスワードランキング
1位 123456
2位 password
3位 12345678
4位 qwerty
5位 12345
6位 123456789
7位 letmein
8位 1234567
9位 football
10位 iloveyou
(米スプラッシュデータまとめ)
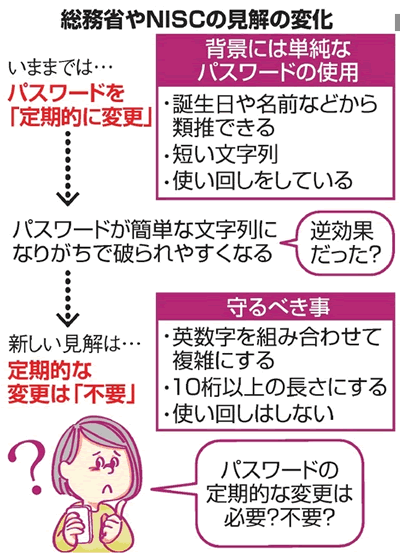
総務省やNISCの見解の変化
(以上、朝日新聞より引用)
■ ■
ほんとうに困っています。
パスワードを忘れます
私のトシのせいだけではないようです。
若い人でも、
iPhoneを設定するためのパスワードや、
LINEのパスワードを忘れて困っている人を見ます。
■ ■
私の知人は、
パスワード管理ソフトを使っていましたが、
iPhoneがバージョンアップした時に、
パスワード管理ソフトが使えなくなってしまい、
おおあわてしていました。
私たち医療機関が困るのが、
オンライン請求です。
定期的にパスワードの変更を求められます。
パスワードを変更しないと、
請求できない仕組みになっています。
■ ■
総務省が方針を変えてくれたので、
そのうちオンライン請求も、
同じパスワードで請求できるようになると思います。
私は、
パスワードを盗んで悪用した人を、
厳罰に処する法律がいいと思います。
パスワードを盗んで悪用すると、
懲役20年だったら、
悪用する人が減るように思います。
医学講座
老後への備え方⑨ 支出の把握は年間を通じて
昨日、札幌に帰ってきました。
札幌は寒いです。
まだコートが必要です。
私は自転車通勤なので、
冬のコートと手袋のままです。
それでも寒いです。
日本は南北に長い国だと、
身にしみて感じています。
■ ■
楽しみにしている朝日新聞の連載が、
昨日(平成30年4月15日(日))の朝刊に載っていました。
朝日新聞の記事をご紹介させていただきます。
(なるほどマネー)老後への備え方⑨ 支出の把握は年間を通じて
■Reライフ 人生充実
老後資金をためなくてはいけないのはわかるのですが、どこから手をつければいいのでしょうか。貯蓄のコツはありますか。
◇
老後資金づくりのために貯蓄額をアップさせるには、家計の現状把握が必要です。コツは「年間」を通じて支出を振り返ること。家計簿をつけていなくても作成できる仕組みがあるので、安心して始めてみましょう。
まず、支出の項目ごとに「毎月の支出」と「年数回の支出」に分けましょう。食費や公共料金のように毎月必要な支出は「毎月」欄に平均額を記入します。固定資産税や交際費のように、毎月ではなく年数回の支出は「年数回」欄を使います。
現役時代なら、「年数回」はボーナスから捻出できますが、年金生活ではボーナスはありません。現役で働いている人は、ボーナスをあてにした支出がどの程度あるのか知っておくことが大切です。
二つ目のポイントは、「基本生活費」をきちんと把握することです。住宅ローンの返済額や保険料は、通帳などを見るとはっきりわかります。しかし食費や日用品といった細かな生活費は、日々の記録がないとわからなくなるでしょう。
そこで「基本生活費」を「①口座引き落とし」と「②お財布支出」の二つに分けます。
基本生活費は、公共料金など銀行などの口座から引き落とされる費目をまとめます。通帳から集計できます。
お財布支出は、口座から現金を引き出して財布に入れた金額を1カ月分、合計して記入します。引き出したお金を何に使ったかは書きません。年間支出の合計額をはっきりさせることを目標にしましょう。
これらを年間支出シートにして記入すると、色々気づくことがあるはずです。各項目の「年間合計」を見ると、月々は多額にみえなくても、年間では大きな出費になっているものがあるでしょう。
定年前の50代は、「メタボ」な家計になっていることが多いです。やみくもに節約をするより、まず現状を把握したうえで、「ここから毎月2万円減らした予算でがんばろう」と、各項目を縮小してやりくりしてみましょう。月2万円の支出減は、年間では24万円減になります。
50代は生命保険料の支出も多いです。家計の担い手の生命保険料が月2万円弱。さらに月数千円の医療保険やがん保険に夫婦で複数加入し、月4万~5万円の保険料となるケースも少なくありません。年間では48万~60万円にもなります。
保険は定年になってから見直せばよい人もいます。しかし早く見直せば、その分多くの老後資金をためられます。4万円の保険料を半分にできれば年24万円ためられます。保険の見直しは次回で詳しく説明します。
このほか、通信費は携帯、固定電話、ネット、有料テレビなどで月に計4万円以上のケースもあります。格安スマートフォンへの切り替えなども検討してみましょう。
「生活費」「保険料」「通信費」の三つの見直しだけでも、年間60万円前後の支出を減らし、老後資金に回すことも可能です。まず支出を「見える化」するのが大事なのです。=全11回
(ファイナンシャルプランナー・深田晶恵)
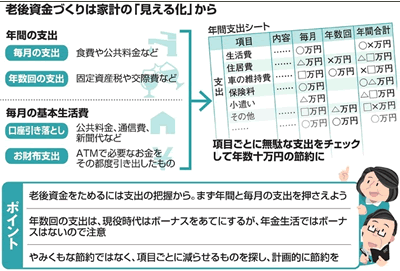
老後資金づくりは家計の「見える化」から
(以上、朝日新聞より引用)
■ ■
本間家でも、
よく奥さんと喧嘩になりました。
えっ?
お金がない?
どうして?
よくよく調べてみると、
お金がない原因が私のことが多かったようです。
仕事に使うからと、
北大生協で買ったMacが原因のことがありました。
昔はMacもとても高かったです。
■ ■
お金と夫婦げんか
用心していても、
お金はあっという間になくなります。
札幌美容形成外科では、
お給料の振込も、
業者さんへの振込も、
全部私がしています。
それでも経営は大変です。
■ ■
クリニックの経理は、
東京のアトラス総合事務所にお願いしています。
信頼できる会計事務所です。
予想数
納税額
…をはっきりと数字で示してくださいます。
家計でも、
年間の出費を表にして、
わかりやすくするのは有用だと思います。
医学講座
第61回日本形成外科学会(福岡)⑤
3日間の日本形成外科学会を終え、
札幌に帰ってきました。
札幌は寒いです。
5日も休むと、
仕事がたくさん待っています。
従業員のお給料の計算、
明日から使うタイムカードの準備、
全部私が一人でやっています。
■ ■
第61回日本形成外科学会で印象に残った講演です。
特別講演2
4月12日(木)17:00~18:00第2会場
司会:清川兼輔(久留米大学医学部形成外科・顎顔面外科学講座)
SL2 健康長寿社会に向けて
横倉義武(公益社団法人日本医師会会長、世界医師会会長)
日本形成外科学会総会で、
日本医師会会長の講演は私が知る限りはじめてです。
■ ■
横倉義武先生は、
清川兼輔教授の久留米大学医学部の先輩で、
清川先生が若い頃に、
横倉先生の病院にアルバイトに行ったことがあり、
横倉先生とご一緒に緊急手術もなさったことがあったそうです。
そのご縁で、
わざわざジュネーブから講演にいらしてくださいました。
■ ■
横川先生のご講演をお聞きして、
日本医師会は、
ちゃんと形成外科のことも考えていてくださる、
…と強く感じました。
健康長寿社会
…のために形成外科が必要であると、
世界医師会会長がわかってくださっていると理解できました。
今回の学会に参加してよかったと思いました。
清川先生、
あらためてありがとうございました。
医学講座
第61回日本形成外科学会(福岡)④
3日間の第61回日本形成外科学会が終わりました。
とても有意義な学会でした。
学会長の久留米大学医学部形成外科清川兼輔教授、
久留米大学医学部形成外科教室の皆さま、
ありがとうございました。
福岡でたっぷり勉強させていただきました。
■ ■
学会長の清川兼輔教授は、
私とほぼ同年代の教授です。
清川教授が、
会員懇親会の会長挨拶で言われた言葉が印象的でした。
久留米大学医学部を卒業して、
形成外科医になると言ったところ、
お母様から反対されたそうです。
■ ■
私の親は反対しませんでしたが、
清川先生のお母様は、
そんな(美容整形の)医者になるために、
あなたを医学部に入れたのではない。
形成外科医になって、
ちゃんと家族を養っていけるのか?
…とご心配なさったそうです。
■ ■
九州男児の母は、
ご子息の将来のことを心配なさったのだと思います。
清川先生の学会運営を見て、
形成外科医が、
皮膚科とか、
美容外科をやらなくても、
形成外科の保険診療だけで、
ちゃんと食べて行けるようにしたい
…という強い思いを感じました。
■ ■
私も清川教授と同じ思いです。
形成外科だけで、
(美容外科や)
(皮膚科を標榜しなくても)
ちゃんと食べて行けるようにしたい。
…とあらためて思いました。
札幌美容形成外科も、
形成外科の保険診療をメインにして、
私の残された人生を送ろうと思いました。
清川会長、いいお言葉をありがとうございました。
医学講座
第61回日本形成外科学会(福岡)③
半年ぶりに出席した学会は勉強になります。
第61回日本形成外科2日目は、
いろいろなトラブルの勉強をしました。
パネルディス カッション6
4月12日(木)10:30~12:00
第3会場 座長:武田 啓(北里大学医学部形成外科・美容外科学)
一瀬晃洋(神戸大学医学部附属病院美容外科・形成外科)
注入療法後(脂肪、フィラー、PRP 他)のトラブルもしくは不満足な結果に対するリカバリー
PD6-1 摘出手術を要した異物注入後遺症患者の検討
野本俊一(日本医科大学形成外科)
PD6-2 ヒアルロン酸注入後の有害事象に対するリカバリー
野本俊一(日本医科大学形成外科)
PD6-3 美容目的のフィラーよる合併症に対する当科の治療方針
岩山隆憲(神戸大学医学部附属病院美容外科)
PD6-4 注入療法後の顔面変形・組織の異常増殖とそのリカバリー
宮田成章(みやた形成外科・皮ふクリニック)
PD6-5 ヒアルロン酸注入事故に対する取り組み
牧野太郎(福岡大学形成外科、牧野皮膚科形成外科内科医院)
■ ■
私が以前から報告している、
ヒアルロン酸や他の注入剤によるトラブルです。
なんちゃって医だけではなく、
形成外科専門医が注入しても、
トラブルになることがあります。
注射くらいなら
安いところでしよう
どうせ同じでしょ?
…なんて絶対に思わないでください。
血管閉塞というこわいトラブルがあります。
学会に出なければわからないところでした。
医学講座
第61回日本形成外科学会(福岡)②
福岡は暖かでいいお天気です。
札幌と2ヵ月くらい違う印象です。
芝桜が咲いています。
学会初日にお聞きした、
特別講演が印象的でした。
わざわざサンフランシスコからいらしてくださった、
広島原爆の被爆者で、平和の語り部
笹森恵子様の講演です。
■ ■
特別講演1
4月11日(水)11:00~12:00 第1会場
司会:平野明喜(日本赤十字社長崎原爆病院)
SL1 笹森恵子ヒロシマ・ナガサキ平和プロジェクト
笹森恵子ささもりしげこ( 名誉人文学博士、広島原爆の被爆者、語り部)
今年6月のお誕生日が来ると86歳だそうです。
とてもしっかりした女性でした。
■ ■
笹森さんが、
広島の原爆によって熱傷を受傷し、
ご両親が熱傷の治療をしてくれたこと、
東大分院で、
林田先生に手術をしていただいたこと、
米国で25人の仲間とともに、
熱傷瘢痕拘縮の治療を受けたこと、
原爆の悲惨さを全身で説明してくださいました。
■ ■
私が一番驚いたのは、
私の恩師、
大浦武彦先生が発言され、
昭和32年に笹森さんのことが新聞に載り、
形成外科というのがまだ知られていない時に、
米国で治療を受けたと新聞記事で知って、
形成外科医への道を選んだ
…とお聞きしたことでした。
今までお聞きしたことがありませんでした。
日本に形成外科がなかった時代に、
米国まで行かれて治療を受け、
世界平和のために貢献していらっしゃる、
笹森恵子しげこさんのお話しが印象的でした。

医学講座
第61回日本形成外科学会(福岡)①
今日から福岡で第61回日本形成外科学会です。
久しぶりの学会は新鮮です。
知り合いの先生や業者さんに何人もお会いしました。
無事に移転できたことを喜んでいただきました。
ありがたいことです。
今日は朝から眼瞼下垂のシンポジウムを聞きました。
■ ■
シンポジウム1
4月11日(水)9:00~10:30 第1 会場
座長:松尾 清(松尾形成外科・眼瞼クリニック、信州大学医学部形成再建外科教室)
村上 正洋(日本医科大学武蔵小杉病院眼科・眼形成外科)
先天性眼瞼下垂の開瞼・閉瞼機能と整容のリカバリー
SY1-1 先天性眼瞼下垂の再手術の工夫:ミュラー筋機械受容器伸展回復で前頭筋を動かし大腿筋膜で瞼板を挙上する
松尾 清(松尾形成外科 眼瞼クリニック、信州大学医学部形成再建外科学教室、浜松医科大学附属病院形成外科)
SY1-2 当科における先天性眼瞼下垂手術
清水 雄介(琉球大学 医学部 附属病院 形成外科)
SY1-3 片側性先天性眼瞼下垂の長期観察例における開瞼・閉瞼・視力対する機能的評価と整容的評価
坂原 大亮(大阪市立総合医療センター 形成外科)
SY1-4 先天性眼瞼下垂:開瞼・閉瞼・整容の3 条件をバランスよく満たすための筋膜吊り上げ術
権太 浩一(帝京大学 医学部附属溝口病院 形成外科)
SY1-5 先天性眼瞼下垂症に対する大腿筋膜移植法の改良~自然な開閉瞼のために
一瀬 晃洋(神戸大学大学院医学研究科形成外科学)
SY1-6 前頭筋吊り上げ術後の合併症~大腿筋膜による過矯正とPTFE シートによる低矯正~
小久保健一(藤沢湘南台病院 形成外科)
■ ■
先天性眼瞼下垂症は、
生まれてきた赤ちゃんの目が開きにくい病気です。
手術方法や、
手術時期が難しい疾患です。
大腿筋膜移植が一般的な手術法です。
ご両親としては、
一日も早く赤ちゃんの目を治してあげたいと願います。
■ ■
大腿筋膜移植は難しい手術です。
術者によってやり方が微妙に違います。
手術結果も、
術者や施設によって違います。
お母さんたちが困っています。
体験記やブログもネットで見かけます。
今日のご発表で私が感動した術式がありました。
■ ■
SY1-2 当科における先天性眼瞼下垂手術
清水雄介(琉球大学医学部 形成外科)
琉球大学医学部形成外科の、
清水雄介教授のご発表です。
清水教授の手術法は、
0歳~2歳の、
重度の先天性眼瞼下垂症に、
ナイロン糸を使って吊り上げる手術を行っています。
■ ■
大腿筋膜を使う方法より低侵襲で、
小さな子供さんの目が、
実によく治っていました。
私が会場で、
自分の孫がこの病気だったら、
清水先生に手術をしていただきたい。
…と言いました。
沖縄までこの手術を受けに行く価値があります。
他にもためになる講演がありました。
また明日、続きを書きます。
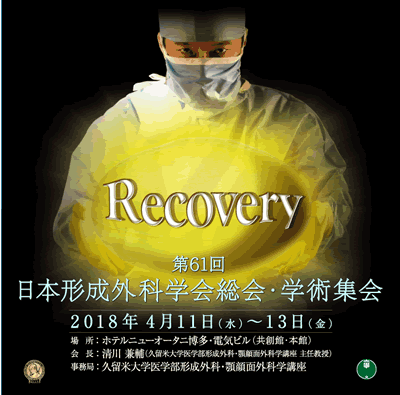
医学講座
半年ぶりに学会出席です
今日から福岡に行きます。
昨年秋から、
学会に出席していません。
お正月も、
どこにも行けませんでした。
ひたすら引越し準備をしていました。
不要な書類を整理していました。
■ ■
クリニックの断捨離は、
予想以上に大変でした。
紙カルテをスキャンして、
電子カルテに保存するだけでも、
かなり大変でした。
その紙カルテを、
シュレッダーにかけるのも大変でした。
■ ■
約半年間準備しましたが、
それでも移転は大変でした。
余計な書類もたくさん持ってきてしまいました。
今日は福岡への移動日です。
形成外科学も毎年進歩します。
新しい手術法や治療法が出てきます。
学会では新しい治療法の検証もあります。
福岡で勉強してきます。
4月15日(日)まで休診します。
医学講座
望まない妊娠に注意
今日は2018年4月9日(月)です。
私は2018年に入ってから、
休みがありませんでした。
ようやく移転できました。
明日から、
福岡の第61回日本形成外科学会に行きます。
札幌美容形成外科は4月15日(日)までお休みです。
■ ■
4月に入って、
入学式も済んだ今頃は、
美容形成外科もひまになります。
毎年この時期に日本形成外科学会があります。
昨年は大阪、
一昨年は福岡でした。
来年は札幌で開催されます。
■ ■
4月から大学生になった若者や、
専門学校に進学した人への、
口うるさいおやじからの助言です。
留年
…と
(望まない)妊娠
…はしないように!
気をつけてください。
■ ■
センター試験で800点以上取るような成績優秀者でも、
国公立大学に合格した成績優秀者でも、
(望まない)妊娠
…をしてしまう人がいます。
彼女を妊娠させてしまった人もいます。
進学校と呼ばれる高校でも、
予備校でも、
受験勉強は教えても、
(正しい)避妊法は教えません。
■ ■
先日の朝日新聞の記事、
性教育に指導、現場困惑 「避妊と言わず、生徒学べるのか」
…で紹介されていた、
NPO法人「ピルコン」には、
ためになる知識がたくさん書いてあります。
男子学生にも、
ぜひ読んでいただきたいです。
■ ■
大学や専門学校に入学して、
新しい生活をはじめて、
彼氏や
彼女
…を見つけるのはいいことです。
♡彼女♡が妊娠してしまった!
…ということがないように、
正しい知識を身につけてください。
女性の方は正しい知識で、
自分の身体は自分で守ってください。