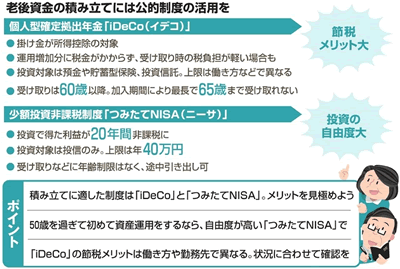医学講座
移転とオンライン請求2018
南舘ビルに移転して順調に診療を続けています。
私のように移転しなければならないとか、
移転をした医療機関への助言です。
隣のビルでも、
引越しすると、
新たな医療機関としての届出と承認が必要です。
一番大変なのが、
医療法人の認可です。
北海道知事が認可します。
■ ■
私のように、
移転直前まで、
移転先が決まらない時は大変です。
原則として、
2㎞以内の範囲が、
遡及指定そきゅうしていを受けられる条件です。
他府県への移転は、
まったくの新規扱いになります。
札幌美容形成外科は、
近くに移転できてよかったです。
■ ■
医療機関にとって大変なのが、
レセプトという診療報酬請求です。
札幌美容形成外科も移転したので、
また新たに電子証明書を取得し、
新しい接続用のIDとパスワードをいただきました。
電子証明書は4,000円もします。
前の電子証明書の有効期限が残っていたのに、、、
もったいない話しです。
■ ■
この新しい電子証明書用の、
IDとパスワードが、
昨日ようやく届きました。
請求業務は毎月5日から10日までです。
幸い、
自分で設定できたので間に合いました。
もしトラブルになったら、
5月10日の締め切りに間に合わない可能性があります。
何でも電子化の世の中ですが、
もう少し簡単にしてほしいです。
AMAZONも楽天も
引越しても簡単に注文できます。
院長の休日
大通公園のチューリップ
南舘ビルに移転してから、
私の通勤経路が変わりました。
毎日、大通公園を通って通勤しています。
札幌の都心なのに、
緑がきれいです。
チューリップが満開です。
私の他にも写真を撮っている方がいらっしゃいました。
■ ■
下の写真が今朝の大通公園です。
♪咲いたさいた♪
♪チューリップの花が♪
…と口ずさんでいる声が聞こえてきました。
私の近くで写真を撮っていらした方でした。
緑がとてもきれいです。
■ ■
今朝の札幌は寒いです。
北海道の5月は、
寒くなったり、
あたたかくなったりを繰り返します。
もう少しすると、
ライラックの花が咲きます。
緑が美しい街はいいです。


昔の記憶
私の欠席日数
昨日の院長日記、
橋本順子先生(ライオン)で、
高校時代のことを思い出しました。
西高一年生の頃
札幌西高の想い出
私が札幌西高校へ入学したのが、
1970年4月(昭和45年4月)です。
■ ■
15歳のけんいち少年はひ弱でした。
よく風邪をひいて、
学校を休みました。
欠席日数が多いので、
自治医大の入試で面接官から、
きみは高校をよく欠席しているが、
そんなに身体が弱くて僻地の医師になれるのか?
…と質問されたのを覚えています。
■ ■
橋本順子先生は、
まさか?
あのひ弱な、
本間くんが、
医者になれるなんて、
きっと思っていなかったと思います。
成績も医学部に合格できるとは、
到底考えられない低空飛行でした。
■ ■
私の欠席日数は、
高校1年生10日
高校2年生15日
高校3年生14日
特に毎年1月~3月の、
3学期に多い傾向があります。
とにかく、
よく風邪をひいていました。
■ ■
欠席日数は、
高校の時の通知票に書いてあります。
実家から持ってきてここ(私の部屋)にあります。
通知票の中味は、
とても公開できるものではありません。
西高1年生の時は、
5段階評価の5はゼロです。
これでも医者になれたのです。
私が医者になれたのは、
予備校でお世話になった、
矢野雋輔(やのしゅんすけ)先生
…のおかげです。
昔の記憶
橋本順子先生(ライオン)
今日は2018年5月5日、子供の日です。
今朝、北海道新聞朝刊を読んでいると、
見たことがある女性が載っていました。
間違いない!
橋本順子はしもとまさこ先生だ!
私が大夕張の山奥から出てきて、
札幌西高校に入学した時の、
1年8組の担任が橋本順子先生でした。
■ ■
順子と書いて
まさこと読みます。
お茶の水女子大学を卒業され、
札幌西高校で世界史を教えていらした、
才女の先生です。
ニックネームはライオンでした。
本名を知らず、
ライオンという名前だけ覚えている同窓生も多いようです。
獅子しし子先生と呼んだ西高の後輩もいました。
■ ■
平成30年5月5日、北海道新聞朝刊(札幌版)の記事です。
札幌の元教員橋本さん
友好のバナナ配達21年
フィリピンの農業者支援
札幌市西区の元高校教員橋本順子さん(81)は定年退職後の21年間、無農薬のフィリピン産バナナを自ら仕入れ、市内の仲間にボランティアで配達している。途上国の農産物を適正価格で取引し、生産者の暮らしを守るフェアトレードを支えるためだ。毎月120㌔約80人分。「フィリピンで頑張る農業者と、札幌の人々の橋渡しをしたい」と話している。(石川泰士)
4月中旬、橋本さんは手稲区内の配達先で車を降り、はき慣れた運動靴できびきび歩く。ベルを鳴らし「バナナをお持ちしました」と明るい声で届ける。
配達しているのはフィリピン南部のバランゴンバナナ。山間部に自生し、農薬や化学肥料を使わず収穫される。大きさはふぞろいだが、やさしい甘さがあるフェアトレードの商品だ。東京の商社を通じて取り寄せ、仕入れ値に配達のガソリン代を加えた1㌔600円で届けている。
このバナナを知ったのは札幌西高の社会科教員だった1995年。途上国の農業者を支えるフェアトレードのバナナを知り、実際に仕入れ、授業で取り上げた。
高校を定年退職した97年、「食べてみたい」との友人の声を受け、試しに20㌔仕入れて4、5人で分けた。昔の教え子の保護者に薦めると評判になり、定期的に仕入れを始めた。
毎月1㌔の配達を受ける手稲区の牧師清水和恵さん(60)は30年前にフィリピンで、低賃金の農園労働者を見た。「バナナを食べると、誇りを持って働く生産者が目に浮かぶ」と話す。
橋本さんは実際にフィリピン南部の現場を訪れている。バナナの収入で自立した生産者の暮らしをみて、活動に手応えを感じたという。
今春からは、市民活動で出会った若い仲間が配達を手伝うようになった。「体力の続く限り、バナナを届けたい」と力を込める。

フィリピン産無農薬バナナを届ける橋本順子さん(左)
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
橋本先生らしいなぁ~
81歳になっても、
すごいなぁ~
札幌西高校には、
新琴似のご自宅から、
カローラで通勤されていた記憶があります。
お元気そうでよかったです。
橋本先生には申し訳ございません。
私は世界史はまったくできませんでした。
先生ごめんなさいです。
昔の記憶
GWなのに寒いです
今日は2018年5月4日(金)です。
みどりの日で祝日です。
札幌美容形成外科は15:00まで診療をしています。
GWに治療を希望される患者さんが多いためです。
明日2018年5月5日(土)も15:00まで診療をします。
2018年5月6日(日)は休診日です。
■ ■
通勤途中で大通公園のチューリップが咲いていました。
ピンクのきれいなチューリップが満開です。
サクラは散りはじめています。
ピンクの花が、
下に落ちてきれいです。
天気は曇りです。
■ ■
札幌美容形成外科では、
寒いので暖房を入れています。
GWでも、
北海道では寒い日があります。
まれに、
雪が降ることがあります。
お天気だけは自由にできません。
■ ■
寒いゴールデンウイーク
2013年5月2日の院長日記です。
今日から2016年5月です
2016年5月1日の院長日記です。
2013年と2016年も寒かったようです。
今年はあたたかくなった後で、
寒い日になりました。
体調に気をつけて風邪を引かないように注意しましょう。
院長の休日
今年はエゾリスをあきらめました
今日は2018年5月3日です。
2016年から楽しみにしていた、
浦臼神社のエゾリスくんを、
今年はあきらめました。
昨夜から雨が降っていて、
今朝も雨でした。
■ ■
ネットで読売新聞のサイトを見つけました。
2018年5月2日に公開された動画です。
今年は移転・引越しで疲れているので、
ネットの動画でがまんします。
何でもあきらめない主義の私ですが、
お天気にはかないません。
来年は会えるといいなぁ~
■ ■
春を彩る花畑にエゾリス
北海道浦臼(うらうす)町の浦臼神社の境内で、群生する青色のエゾエンゴサクと紫色のカタクリの花が見頃を迎えている。
約1週間限定の「春を彩る花畑」に、周囲の森にすみつく野生のエゾリスが時折姿を見せ、立ち上がったり、花の間を駆け回ったりしている。浦臼町商工観光係によると、花畑の見ごろはゴールデンウィーク期間中という

=北海道支社報道課 鷹見安浩撮影
2018年5月2日公開
(以上、読売新聞WEB版より引用)
医学講座
脱毛料金値下げについて2018
昨日の院長日記、
脱毛料金を改定しました2018に、
なっちゅんさんからコメントをいただきました。
脱毛料金の改定……
引越しされたのに値下げですか
驚きました!
悩んでる方は行きやすくなりましたが
先生、大丈夫ですか?
収支は赤字にはなりませんか?
■ ■
ご心配いただきありがとうございます。
私の予測では、
赤字にはなりません。
脱毛の歴史2015です。
今から20年前に登場した脱毛レーザーは、
画期的な機器です。
当時のレーザー脱毛機器はとても高価でした。
レートも一ドル130円以上だったと記憶しています。
日本に輸入すると、
一台3,000万円以上しました。
札幌で一番早く導入されたのが、
皮膚科の山家英子先生でした。
武藤靖夫先生(札幌中央形成外科)が、
札幌で2番目でした。
■ ■
今では、
レーザー脱毛があたりまえですが、
当時は、形成外科の偉い先生から…
レーザーで毛が抜けるわけがない!
絶対にまた生えると言われました。
その後、
レーザー脱毛機も進歩しました。
札幌美容形成外科で使っているのは、
冷却ガスが出るタイプのGentleLASE(キャンデラ社製)
という機種です。
■ ■
GentleLASEは、
日本の医療機関で一番多く使われている機器です。
レーザーはお金がかかります。
メンテナンス費用が毎年60万円(税別)以上かかります。
困るのが故障です。
札幌美容形成外科では、
予備機を準備しています。
飛行機と同じで、
同じ機種が複数あると、
交換部品も共通です。
維持費も安くできます。
値下げは、
毛で悩んでいらっしゃる方に、
少しでも快適になっていただきたという私の願いです。
値下げしても丁寧に照射します。
医学講座
脱毛料金を改定しました2018
今日は2018年5月1日です。
来年の5月1日には新元号になっています。
クリニックの移転問題でご迷惑をおかけしていた、
レーザー脱毛を再開しました。
2018年4月から、
新しい料金体系にしました。
女性の脱毛料金を値下げしました。
■ ■
私の美容外科医としての思いです。
自分には何の責任もないのに、、、
女の子なのに、、、
毛がぼうぼうの人がいます。
目は二重で、
鼻も高くて、
美人なのに、
毛深くて悩んでいる女性がいます。
■ ■
札幌美容形成外科には、
そんな悩める女性がたくさん来院されます。
毛が原因で、
顔のニキビが悪化することがあります。
女の子なのに、、、
おへそから、
お尻まで、
くまさんのような方がいらっしゃいます。
■ ■
札幌美容形成外科で人気の、
レーザーフェイシャルは、
一回9,600円から、
一回8,000円に値下げしました。
ビキニラインの脱毛も、
一回9,600円から、
一回8,000円に値下げしました。
■ ■
困っている方が多い、
VIOの脱毛は、
おへそ下から、
VIO
まで脱毛して、
一回19,600円です。
初回だけ安いのではなく、
ずーっと同じ値段です。
■ ■
札幌美容形成外科からのお願いです。
脱毛を希望する部位は、
ご自分で剃っていらしてください
看護師が剃毛をすると、
時間がかかります。
申し訳ありませんが、
2018年5月からは、
剃毛料金1,000円がかかります。
■ ■
男性の脱毛は、
申し訳ありませんが料金はそのままです。
人によっては、
ひげの脱毛だけで1時間もかかる方がいらっしゃいます。
体の脱毛は男性も女性も同じ料金にしていました。
男性の方が体格がよく、
同じ部位でも面積が広く時間がかかります。
ヒゲ脱毛の料金値上げはしませんが、
男性の脱毛はヒゲだけに限らせていただきます。
申し訳ございません。
医学講座
平成30年4月30日
早いもので今日で2018年4月が終わります。
今朝の新聞に、
【平成】があと一年で終わり、
2019年5月から【新元号】になると書いてありました。
私は平成元年4月1日から、
市立札幌病院皮膚科に勤務しました。
1989年4月1日です。
■ ■
札幌市役所本庁に行って、
札幌市長から訓示を受けました。
辞令は、
病院に戻って院長からいただいた記憶があります。
札幌市の秘書課職員の方が、
市長が来られる前に【注意】をしてくださいました。
市長が訓示をされる時には、
市長の目を見てください。
…と言われたのが印象的で今でも覚えています。
■ ■
当時の市立札幌病院も赤字でした。
形成外科の手術器械は購入してもらえず、
形成外科メモリアル病院の、
本田耕一院長にお願いして、
手術器械をお借りしたことを覚えています。
形成外科で使う、
手術用顕微鏡もありませんでした。
何もないところではじめました。
■ ■
私の平成時代は、
激動の歴史です。
信じてはいけない人にだまされ
48歳で職を失いました
札幌美容形成外科を開業し、
院長日記をはじめました。
2019年5月からの新元号はどんな時代になるのか?
残された人生を悔いのないように生きたいと思います。
医学講座
老後への備え方⑪ 積み立て、特長異なる2制度
今日は2018年4月29日です。
札幌でもチューリップが咲きはじめました。
南舘ビルに移転してから、
毎朝大通公園を通って通勤しています。
大通公園には、
札幌駅前通りにはなかった、
たくさんの花壇があり癒されます。
■ ■
楽しみにしていた朝日新聞の
老後への備え方、
なるほどマネー講座は今日で最後です。
平成30年4月29日、朝日新聞朝刊の記事です。
(なるほどマネー)老後への備え方⑪ 積み立て、特長異なる2制度
■Reライフ 人生充実
保険を見直して浮いたお金で毎月積み立てようと思います。どのような制度があり、どんなメリットがあるのでしょうか。
◇
老後の資金を積み立てる手段として、税金面でメリットがある個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」と、少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」という二つの制度が最近注目されています。
iDeCoから見てみましょう。
税金のメリットは、①掛け金は所得控除の対象でその年の所得税と翌年の住民税が安くなる、②掛け金を運用して増えた分には税金がかからない、③積み立てたお金を受け取る時は退職金や公的年金の税制が適用され、税負担が軽くなる場合がある、の3点です。
年収600万円の会社員や公務員で、扶養家族は妻と高校生の子1人の場合、月1万2千円ずつ積み立てると、所得税と住民税の節税額は年2万9100円。掛け金に対し、約20%の節税メリットが得られます。
加入時は自分で選んだ金融機関で専用口座を開きます。手数料や取り扱う商品は、各窓口で異なります。
口座を開いた金融機関が扱う預金、貯蓄型保険、投資信託の中から選んで積み立てます。
掛け金は月5千円以上で、千円単位で決められます。上限は働き方や勤務先により異なります。
限度額は会社員・公務員は月1万2千~2万3千円、専業主婦(主夫)は月2万3千円。詳しくは勤務先に確認しましょう。
老後資金づくりの積立制度のため、受け取りは60歳以降です。受取額は、掛け金より増える場合も、減る場合もあります。値動きのある投資信託はもちろん、預金や貯蓄型保険でも、手数料以上に利息を得られないと、掛け金より増えない可能性があります。
一方、つみたてNISAは、投資で得た利益への税金が、一定期間非課税になるメリットがあります。
投資信託で10万円の利益が出たとします。本来は利益に約20%、約2万円の税金がかかりますが、NISA口座を利用すると非課税となり、利益は丸々手取りとなります。
積み立て限度額は年40万円、非課税期間は20年です。金融機関で専用口座を開設し、商品を選んで積み立てます。購入できるのは投資信託のみで、預金は対象外です。
iDeCoとつみたてNISAの両方で積み立てできるほど、家計に余裕のある人は多くないでしょう。ではどちらがいいのでしょうか。
給与への節税効果があるiDeCoは、会社員や公務員にメリットが大きいです。ただ、60歳までの加入期間が10年に満たない場合、最長で65歳まで積み立てたお金を受け取ることができません。60歳以降は運用だけで積み立てをできず、節税メリットは受けられないのです。
50歳を過ぎて初めて資産運用をする人にiDeCOは大きなメリットはないでしょう。年齢制限がなく自由度が高いつみたてNISAで運用の練習を始めるといいでしょう。
(ファイナンシャルプランナー・深田晶恵)
◇
「老後への備え方」は今回で終わります。次回から「『終活』を考える」を掲載します。
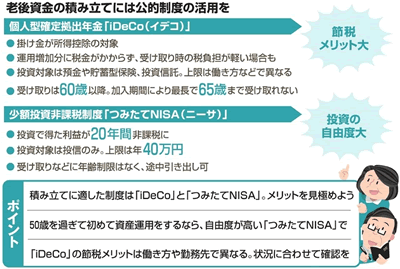
老後資金の積み立てには公的制度の活用を
(以上、朝日新聞より引用)
■ ■
現在63歳の私は、
iDeCo(イデコ)はダメで、
少額投資非課税制度 つみたてNISA(ニーサ)
…ということは理解できました。
私はこの説明の中にあった、
受取額は、
掛け金より増える場合も、
減る場合もあります。
…という文字を見ただけで拒否反応です。
■ ■
昔、新婚の頃に、
奥さんが釧路労災病院の宿舎に訪ねてきた、
○○証券のセールスマンに言われて、
証券会社の商品を買ったことがありました。
奥さんは、
元本割れない
…というセールスマンの言葉を信じて、
貯金を証券会社に預けました。
■ ■
何かでお金が必要になって引き出す時に、
預けた金額より減っていて、
大喧嘩になったことがありました。
それ以来、
掛け金より増える場合も、
減る場合もあります。
…という言葉には拒否反応が出るようになりました。
■ ■
値動きのある投資信託はもちろん、
預金や貯蓄型保険でも、
手数料以上に利息を得られないと、
掛け金より増えない可能性があります。
つくづくお金は難しいと思います。
美容外科の、
軽微な仮性包茎に限るを連想します。