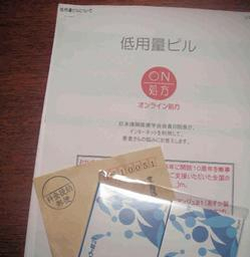医学講座
献血とHIV
平成20年1月24日、朝日新聞朝刊の記事です。
献血でHIV判明100人超
日赤「検査目的やめて」
■ ■
献血時にエイズウイルス(HIV)感染が判明した人が2007年に初めて100人を超えたことが1月23日、日本赤十字社の調べで分かった。
感染者増に加え、検査目的で献血をする人が後を絶たないためとみられる。
日赤は「感染直後は検査をすり抜けて輸血で感染してしまう恐れがある。
検査目的の献血はやめてほしい」と呼びかけている。
■ ■
2007年の献血者総数延べ約494万人のうち、HIVが検出されたのは102人で前年比15人増。
献血者10万人あたり2.065人で、初めて2人を超えた。
(以上、朝日新聞から引用)
■ ■
HIV検査は、保健所では、無料で実施してくれます。
匿名でもOKです。
でも、いくら匿名でも…
保健所に行くのは本人です。
いかにも…
という目で見られる?
と考えるとイヤなものです。
(実際には、そんなことはないと思いますが…)
■ ■
私が、HIV検査を手術を受ける方全員に行うようになったのは、
帯広厚生病院時代からです。
院内感染対策委員会の委員でした。
当時の院内感染対策委員会の委員長が
現在、JA帯広厚生病院院長の川口勲先生です。
■ ■
川口先生は、産婦人科のベテラン医師です。
帯広厚生病院は、北海道内の病院でも、早くからHIV検査を実施しはじめました。
HIV検査の重要性を一番強く認識されているのが、臨床検査技師の方です。
われわれ医師は、担当した患者様の結果しかわかりません。
臨床検査技師は、すべての方の検査結果がわかります。
院長より、よく知っています。
■ ■
私は、臨床検査技師の方から、HIV検査をすすめられました。
毎日、たくさんの検査をしていると、たとえ10万人に2人でも、陽性者に遭遇する確率は高くなります。
HIV陽性者の増加を、肌で感じているのが臨床検査技師さんです。
■ ■
現在、問題になっている肝炎は、血液製剤で感染しました。
医師・看護師などの医療従事者は、血液を通じて感染するリスクがあります。
私の知人の医師でも、誤って針を刺してしまい肝炎になってしまった人がいます。
■ ■
同じことが、HIVでも起こる可能性があります。
将来、何の罪もない人が、HIVに感染してしまう可能性があります。
献血に行って、HIV陽性だったとしても、結果は教えてくれません。
ブラックリストに載るだけです。
■ ■
HIVに感染する可能性があるようなことは、しないのが一番です。
ただ、もし、HIV感染が心配なら、
絶対に献血はやめてください。
HIVに感染していたとしても、検査で見つからない時期があります。
ウインドウピリオドといいます。
ここのHPに詳しく書かれています。
HIV検査は、札幌美容形成外科でも、他の医療機関でも受けられます(有料:当院は1,050円)。
心配な方は、保健所や医療機関で検査を受けてください。
医療問題
出産事故-補償-
平成20年1月24日、朝日新聞朝刊の記事です。
出産事故2,500万円補償
2008年度から-重い脳性まひ救済-
■ ■
政府方針で導入される、出産時の医療事故で重い脳性まひになった子の救済制度について、
厚生労働省所管の財団法人・日本医療機能評価機構は1月23日、子1人当たりの補償額を計約2,500万円とすることを決めた。
事故直後の一時金と、成人するまでの分割給付金に分ける。
■ ■
救済対象となるには出産を扱う病院・医院が保険に加入している必要があり、 同省などが加入を呼びかける。
2008年度中に開始する。
■ ■
救済対象は、妊娠33週以降に体重2,000グラム以上で誕生するなど、通常の妊娠・出産で、重い脳性まひになった子。
年間500~800人程度を見込む。
未熟児や先天的に脳に異常がある子らは原則対象外。
医師に過失がなくても救済されるのが特徴で、産科医不足の一因とされる医療紛争を減らす狙いもある。
■ ■
補償金は、出産後の一時金(500万~600万円)と、
子どもが成人するまで支払われる分割金(1ヵ月当たり約8万円、総額約2,000万円)に分けて給付。
子どもが成人前に死亡した場合は遺族に給付される。
■ ■
医療機関が支払う保険料は出産費用に転嫁されるとみられ、個人負担が3万円程度高くなる恐れがある。
このため同省は、制度開始にあわせて健康保険から支払う出産育児一時金(現行35万円)を引き上げる方針。
(以上、朝日新聞から引用)
■ ■
赤ちゃんは、お母さんのお腹にいる時は、お母さんの血液から、胎盤を通じて酸素をもらっています。
出産と同時に、赤ちゃんは自分で呼吸を始め、『おぎゃぁ!オギャァ!』と言って、酸素を自分で取り込みます。
■ ■
産道を通って、無事に生まれるまでの間に、『何か?』が起こると、赤ちゃんの脳に酸素が届かなくなります。
出産時の脳性マヒは、簡単に説明すると、こういう‘事故’です。
お母さんが健康でも、赤ちゃんが健康でも、事故が起こる可能性はあります。
■ ■
・妊娠33週以降
・体重2,000グラム以上
・通常の妊娠・出産
と条件がついていて、
・未熟児
・先天的な脳の異常
は原則対象外となっています。
■ ■
脳性マヒになるのは、出産時だけではなく
出生前
・胎内感染
・母体の栄養障害や中毒
・胎児の黄疸
・未熟児
出生後
・脳炎
・脳内出血
・中枢神経感染症
などによっても起こります。
1,000人につき2?4人の割合で起こり、
早産児にはその10倍と言われています。
こちらの萬有製薬HPに詳しく記載されています。
■ ■
以前から私が書いているように、どんなに医療が発達しても、100%安全なお産はありません。
お母さんだけではなく、赤ちゃんにも危険は生じます。
不幸にして、悪い状態で生まれた子供を助けてくれるのが、小児科医です。
■ ■
私は、平成元年から平成6年まで、市立札幌病院に勤務しました。
市立札幌病院には、NICUがあり、服部先生、中島先生という、素晴らしい先生が活躍していらっしゃいました。
NICUは未熟児センターと呼ばれていました。
■ ■
私の友人や後輩の子供さんが、1,000㌘にも満たない、極小未熟児で生まれた時に、
見事に助けてくださったのが、未熟児センターの先生でした。
私も、形成外科医として、未熟児センターへよく往診に出かけました。
■ ■
周産期医療ということばがあります。
元気な赤ちゃんを産むには、お母さんのお腹にいる時から、赤ちゃんをしっかり診断して、
もし、異常があれば、生まれる前から治療をしたり、治療の準備をします。
■ ■
産科医はもちろん大切ですが、小児科医も大役を果たします。
残念なことに、産科医も小児科医も、不人気なのが現状です。
今回の出産事故の補償は、一つの保険システムです。
救済されるのは、脳性マヒの方の一部です。
■ ■
国は、少子化対策の一環として、
不幸にして脳性マヒになった子供さんすべてが、救済されるようなシステムをつくるべきです。
生まれてくる子供に罪はありません。
脳性マヒで困るのは、子供の時期だけではありません。
生涯にわたり、ハンディが残ります。
障害者に優しい国づくりが、日本を豊かにすると思います。
未分類
住民票の写し
役所でいただく書類には、戸籍謄本、印鑑証明、住民票などがあります。
この中で、住民票だけ、
『住民票の写し』が正しい日本語だということを、つい最近知りました。
『住民票の写し』は‘住民票’のコピーではありません。
役所に保存してあるのが‘住民票’。
私たちが、役所からお金を払っていただくのが、『住民票の写し』です。
■ ■
ネットバンキングやネット証券など、インターネットを使ったお金の取引が多くなっています。
お金を不正に、やり取りされると困るので、本人確認を厳しくされます。
口座開設にも、さまざまな書類が必要です。
■ ■
昨年、ご紹介した、新生銀行に口座を開設するには、2種類の本人確認書類が必要です。
A.コピー(下記のうち一通)
・運転免許証(変更があれば裏面もコピー)
・パスポート(顔写真のページと住所のページ)
・住民基本台帳カード(変更があれば裏面もコピー)
・各種健康保険証(住所欄があれば裏面もコピー)
・各種年金手帳(住所記載ページもコピー)
・各種福祉手帳(住所記載ページもコピー)
B.原本(コピー不可)(下記のうち一通)
・電話・携帯電話
・電気
・水道
・ガス
・NHK
・当行所定(Yahoo! BB、OCN、nifty、DION、Plala、BIGLOBE、So-net、DTI、ODN、フレッツ)のインターネットプロバイダー
・CATV
の請求書・領収書の原本。
■ ■
新生銀行では、2種類の書類で本人が、本当にそこに住んで、生活しているかどうか?を確認しています。
引っ越して間もないと、請求書が前の住所のままなので、難しいことがあります。
この時は、『住民票の写し』の原本で、証明します。
新生銀行のHPには、『住民票の写し』について、
・ 作成、発行後6ヵ月以内のものに限ります。
・ ご本人さま記載ページだけでなく、発行日、発行者印のあるページまですべてお送りください。
・ 複数ページで発行されたものは切り離さずそのまま全てお送りください。
と書かれています。
住民票の写し(コピーのことではありません)と書かれています。
これだけだと、役所からいただくのが、『住民票の写し』であることは、わかりません。
ただ、コピーはダメだということはわかります。
■ ■
住民票は、役所にある原本のこと。
私たちが、お金を払ってもらうのが『住民票の写し』。
昔は、役所に、紙でできた、住民票という‘札(ふだ)’があって、その写しをいただいていたのでしょう。
今は、戸籍も電子化されています。
『住民票の写し』は、いかにもお役所らしい、古い言葉です。
■ ■
私は、岩井証券という会社に登録してある住所を変更するのに
『住民票の写し』のコピーを送ってしまいました。
書類不備で返送されてきました。
住民票のコピーは受付できかねます。
お手数ですが、添付の「本人確認書類について」を参照の上、送付願います。
と書いてありました。
最初は何のことかわかりませんでした。
よく読んでみて、はじめて、私たちがいただくのが『住民票の写し』であることを知りました。
紛らわしい(マギラワシイ)日本語です。
■ ■
運転免許証や住民基本台帳カードはコピーを送ります。
住所変更をすると、裏面にゴム印と公印で訂正してくれます。
住所変更を証明するために、免許証の表と裏をコピーして送ります。
カード式の健康保険証は、裏面に自分で住所を記入するようになっています。
実際に住んでいない、住民登録もしていない、住所を記入することもできます。
■ ■
運転免許証や健康保険証の裏面には、本人の名前も記号番号も記入してありません。
他人の運転免許証や健康保険証を借りて、裏面に書かれた、他人の住所を‘悪用’してもわかりません。
『住民票の写し』には、前住所、住所を定めた日(移動年月日)も記載されます。
どちらが、正確に新しい住所を証明できるかというと、私はコピーでも『住民票の写し』だと思います。
■ ■
金融機関が、住所にうるさくなった理由は、法律が改正されたからです。
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則
という、長い名前の法律ができました(平成18年9月22日公布)
これにより、平成19年1月4日から、本人確認が厳しくなりました。
■ ■
この法律によると、
運転免許証や健康保険証は、第三者が入手できない、公的証明書。
『住民票の写し』は、第三者も入手できる、公的証明書。
と区別されています。
不思議なことに、金融庁は、HPで『住民票の写し』と言わないで、住民票と記載しています。
■ ■
私は、誤解を招く、『住民票の写し』などという、お役所用語は、死語にしてほしいと思います。
義務教育では、『住民票の写し』が正しい日本語である、とは教えていません。
センター試験にも出ません。
ふつうの日本人は、『住民票の写し』といわれると、住民票のコピーを連想します。
間違いやすいお役所用語は、訂正するべきです。
住所変更は、『住民票の写し』のコピーでもできるようにして欲しいと思います。
医療問題
ピルネット販売?
平成20年1月21日、朝日新聞朝刊の記事です。
ピル、無診察でネット販売
医師法違反も 愛知の医師
■ ■
現役の医師であるクリニックの院長が、低用量ピル(経口避妊薬)をインターネットで全国に販売していることがわかった。
ピルは処方箋(せん)医薬品で、医師の診断と処方箋が必要だが、院長は簡単な電子メールのやりとりだけで販売していた。
医薬品販売業の許可も得ておらず、厚生労働省は医師法や薬事法に違反する疑いがあるとして調査する方針だ。
■ ■
ネットでピルを販売しているのは愛知県丹羽郡にある婦人科や泌尿器科を掲げるクリニックの男性院長(49)。
院長は「オンライン処方」と題したホームページ(HP)を開いている。
HPでは、通常3,150円の低用量ピル1周期(シート)分を2,500円とし、
「2,000円に値下げ」との記載もある。
「どの低用量ピルが適しているか、院長が無料・ボランティアで相談する」と書かれ、
購入希望者には、メールで
①年齢、身長、体重
②健康状態や服用中の薬の有無
③ピルの使用経験――について返信を求めている。
■ ■
取材に応じた院長によると、HPへのアクセスは1日約6万件で、
処方依頼や服用の問い合わせなどのメールが1日60~100件あるという。
■ ■
昨秋、このHPを通じてピルを購入した東京都内の女性によると、ピルの使用経験はなかったが、
「ピルを使用したことがある」
とメールで送ると、
「経験者で、すでに近くの産婦人科で検査も終わっているようですから、低用量ピルの使用はOKと判断しました♪」
と返信があった。
■ ■
料金は2シート分で5,000円(内税)。
指定の銀行口座に入金すると、その日のうちに入金確認のメールがあり、翌日にはピルが届いた。
■ ■
厚労省によると、医師法は、医師が診察せずに診断書もしくは処方箋を交付してはならないと規定している。
また、医師が診察後に処方する場合を除き、
医師の処方箋があっても処方箋医薬品の販売には医薬品販売業の許可や薬局開設許可が必要だが、
愛知県江南保健所によるとクリニックはいずれも無許可だった。
■ ■
専門家らは、ピルを医師の経過観察なしに自己判断で長期間服用すると、乳がんや肝機能障害といった健康被害を引き起こす恐れもあると指摘している。
院長は「メールで患者の健康状態は十分に把握できる。
無診断処方を禁じた医師法の規定は実態にそぐわない。
処方はあくまで医療行為であり、薬事法に基づく無許可販売との指摘は受け入れられない」と話している。(本田直人)
■ ■
患者の利便性考慮
あくまで医療行為
一問一答
院長との主なやりとりは次の通り。
■ ■
-購入希望者とのメールでのやりとりは医療行為と言えるのか。
医療行為だ。ピルの処方を求める患者は、転居などのたびに初診を繰り返す必要があり、その都度、高額の診察料や細かい検査を求められる。
来院後も長時間待たされるが、メールならば好きな時間に健康状態を送信でき、処方がOKだと判断すれば2~3日以内に全国に郵送できる。
ほかの医師が患者の利便性を考えない方が不思議だ。
■ ■
―直接診察しない購入希望者についてもカルテを控えているのか。
当然だ。
パソコンでカルテを作成し、新たに処方する場合、薬の種類や量を逐一上書きしている。国が進める電子カルテを先取りしている。
-医師法や薬事法違反と指摘されているが。
医師法はネット社会の到来より半世紀も前にできた法律であり、医師不足の解消や遠隔地医療の充実を求める世論に照らし合わせても、規定は実態にそぐわない。薬の処方はあくまで医療行為であり、薬事法上の無許可販売にはあたらない。
■ ■
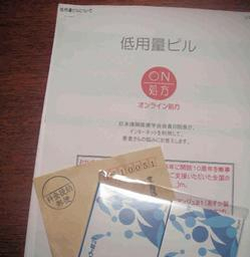
東京都内の女性購入客のもとに郵送されたピル
(以上、朝日新聞より引用)
■ ■
この記事は、朝日新聞が朝刊に掲載。北海道新聞が夕刊でした。
朝日が、(他社を)抜いた記事で、記者の署名入りで力が入った、書き方でした。
朝日新聞社は、医師法違反で、無許可でネット販売をしている。
けしからん医師だ!
と決めつけているようです。
‘ネットで販売で、儲けている’
という、読者へのメッセージが見えてきます。
■ ■
私は、この先生と面識がありませんし、所属学会も違います。
ただ、ネット検索で10年位前から、存じていました。
クリニックの名前は、宮川クリニックです。
先生は、宮川善二郎先生です。
婦人科のことはわかりませんが、包茎手術に関していえば、良心的な先生です。
HPでの包茎や性病についての記載も、正確です。
職員への教育や啓蒙に使わせていただいています。
■ ■
宮川先生は、
日本遠隔医療学会
という学会の会員です。
遠隔医療学会が、薬のオンライン処方を推進しているかどうか?わかりませんが
少なくとも、患者様に危害を加えることは少ないと思います。
■ ■
ピルが欲しければ、宮川先生のオンライン処方に頼らず
ネットで、『ピル、個人輸入』と検索すれば、簡単にサイトが見つかります。
私が検索した範囲では、宮川先生より‘高い’ところが多いようです。
■ ■
朝日新聞社は、もし、ピルのオンライン処方が問題だと取り上げるのでしたら
もっと危険な、個人輸入を取り上げるべきです。
宮川先生は、少なくとも、メールで相談した上で‘処方’しています。
何かあっても、すぐにメールで返信しているはずです。
■ ■
朝日新聞社の記者は、他の婦人科の先生から情報を得て、
宮川先生を取り上げたと、私は推測します。
同業者にとっては、目障りなサイトです。
東京には、たくさんの婦人科やレディースクリニックがあります。
日本国内には、ピルが欲しくても、近くに婦人科がない地域がたくさんあります。
そういう僻地にも、妊娠可能な若い女性はいます。
■ ■
望まれない妊娠を繰り返しているよりは、ピルは役に立ちます。
仕事が忙しくて、受診する機会がない女性もいます。
毎月、耐えられない生理痛に悩んでいる女性にも、ピルが役立つことがあります。
オンライン処方は、そういう、社会的なニーズがあるからヒットするのです。
■ ■
厚生労働省は、この際、古い医師法を見直して
このように、社会的ニーズがある、ネット処方を是非考えて欲しいものです。
家内は‘ネット販売で儲けている、けしからん医師’だと、
TVのワイドショーを見て思ったそうです。
私は、そうは思いません。
先生が自ら、メールの返事を書いて、2,000円では安いと思います。
おそらく、私と同じように、夜遅くまでPCに向かっていると思います。
先生を取り締まる前に、危ない個人輸入に歯止めをかけるべきだと思います。
医学講座
ワキガ手術-通院不要?-
先日、次のようなお問い合わせをいただきました。
他の美容外科では、ワキガ手術を、2回とか3回の通院でしている。
お宅で、何回も通院させるのは、
保険でやって、ちゃんとやっていないからじゃないの!?
という、お電話でした。
■ ■
何度も、私がHPや日記で繰り返しています。
ワキガ手術は、ワキの皮膚を裏側から削る手術です。
どんな方法で手術をしても、必ず皮膚は傷つきます。
傷ついた皮膚を回復させるためには、軟膏を塗ったり、マッサージをしたりする必要があります。
ちゃんと治療しているから、何回も通院するのです。
■ ■
保険診療では、形成外科の再診(通院)は赤字です。
現在の保険制度では、私と看護師が15分もかけて説明して、マッサージをしても軟膏代+490円(再診料別)しかいただけません。
クリニックで処置をした際の、テープ・ガーゼなどの料金は、こちらで負担。
本人には請求できません。
処置だけの場合でしたら、本人負担額は500円程度です。
テープやガーゼの価格を考えると赤字です。
通院が多ければ多いほどクリニックの赤字は増えます。
それでも、通院が必要ですとご説明し、赤字でも通院して処置をしているのは、
キレイに治すために、処置が必要だからです。
■ ■
先日いらした女性の方は、東京でワキガ手術を受けられました。
通院は不要。
その日に手術ができます。
その言葉を信じて…
手術を受けられました。
結果は…
ワキのキズが化膿して、キズがふさがらず、結局、大きなキズが残ってしまいました。
■ ■
私が手術をしても、残念なことに、キズが残る方はいらっしゃいます。
その方の体質により、盛り上がること(ケロイド)や、
皮膚が一部死んで壊死(エシ)になってしまうことがあります。
範囲が広い方は、ワキ中央部の血流が悪くなります。
臭いのキツイ方、
毛の濃い方は
できる限り、汗腺や毛根をキレイに取り除きます。
そうすると、皮膚血流が悪くなり、壊死(エシ)や色素沈着(クロズミ)のリスクが高くなります。
■ ■
キズが目立ったり、黒くなったりした部位は軟膏を塗って治療します。
回復までに一年以上かかることもあります。
それだけ、ワキガ手術は大変なのです。
総合病院の形成外科では、入院手術をすすめます。
入院しても手術後はベッドの上で安静にしているだけです。
自宅でもできることです。
■ ■
手術後にキレイになるかどうかは、
安静を保つこと
ご自身のケアー
タバコを吸わないこと
によって、大きく違ってきます。
■ ■
通院不要は、手術を受ける側にとって、 魅力的な言葉です。
通院不要で、ワキガ手術をしたら…
汗腺をしっかり取らなければ、キズの治りもよいので可能かもしれません。
しかし、臭いを取るのが目的の手術です。
汗腺の取り残しがあれば、必ず臭いが残ります。
一般に『再発』といわれているヤツです。
最初から取っていないのですから、『再発』ではなく『取り残し』です。
■ ■
多くの美容外科では、ワキガ手術は‘簡単です’と説明しています。
難しい手術で、キズが残る可能性があります…
なんて書いたら、お客さんが逃げてしまいます。
形成外科出身の美容外科医は悩みます。
治療方針と‘営業方針’が合わないからです。
私も、雇われ院長だった時に悩みました。
当時も‘安静の必要性’を説明しました。
ですから、手術件数は他院より少なかったかもしれません。
■ ■
自分で開業してからは、保険診療以外ではワキガ手術をしておりません。
お休みが取れない方には、手術をおすすめしません。
赤字でも、
お客さんが減っても、
私は、キズをキレイに治すことを第一に考えています。
残念なことに、これだけ、徹底しても、治りが悪い方がいらっしゃいます。
キズが残った時は、キレイになるまで、責任を持って治療しています。
それは、私が形成外科医だからです。
昔の記憶
受験生の宿
平成20年1月19日朝日新聞朝刊の記事です。
受験生ホテル高級化
少子化 都内で獲得競争
スイート開放「自習室」/脳活性化メニュー
■ ■
高層階のスイートルームを「サロン」として開放したり、
「脳を活性化するメニュー」を提供したり――。
きょう19日に大学入試センター試験が行われ、大学受験シーズンが本番を迎える。
地方から多くの受験生が集まる東京都内のホテルは、次々と高額な受験生プランを打ち出している。
■ ■
受験向けの宿と言えば「格安」を連想しがちだが、受験者数の減少で状況は様変わり。
各ホテルは高級感や違いをアピールして、受験生の獲得にしのぎを削る。
スイートルームを利用した「自習室」。
■ ■?
東京・新宿駅西口の京王プラザホテルは2月から、一泊13万9,000円の41階のスイートルームを、ホテルに宿泊した受験生たちに開放する。
一室はソファで談笑できるスペース、一室はダイニングルームをアレンジした「自習室」だ。
■ ■
受験雑誌や辞書、時刻表はもちろん、お菓子やコーヒーも無料で用意。
夕食には「脳が活性化し記憶力が増す」といわれる脂肪酸の一種「アラキドン酸」を含む肉料理を用意する気の回しようだ。
ホテル側は「部屋に引きこもらずに、リラックス出来るように」と話す。
値段は夕食付きで「2万3,000円~」。
■ ■
中央区のロイヤルパークホテルは近くの水天宮のお守りを用意し、受験生を迎える。
モーニングコールは電話だけではなく、スタッフが直接部屋を訪ねて目覚めを確認。
同じくコーヒーなどが飲めるエグゼクティブラウンジを開放し、交通手段などの相談に乗る女性スタッフも常駐。
値段は2万7,000円前後と高めだが、前年を7割上回るペースで予約が入る。
■ ■
JR東日本系のホテルメトロポリタン(池袋駅西口)では、
合格祈願のメッセージが入ったIC乗車券Suicaをオプションで購入できるプランも。
「受験会場まで、切符を買わずにらくらく乗車できます」。
一泊約2万4,000円など。
ホテルニューオータニ(千代田区)は、便利な立地や加湿器の提供などを売りに3万円や4万円のプランを組んだ。
■ ■
旅行各社によると、一泊1万円以下の格安ホテルも根強い人気だが、今年は全般的に「高め」の傾向という。
背景には、少子化に伴う受験者数の減少がある。
■ ■
今年度の大学入試センター試験の志願者数は約54万人で前年比1.8%減。
定員割れを避け、少しでも優秀な学生を確保しようと地方で「出張入試」をする大学も増えた。
その分、受験生は長期上京する必要がなくなった。
■ ■
JTB広報室の関口和彦マネジャーは
「申し込みに来るのはほとんどが親。
2、3泊なら多少高くても立地や環境を優先し、
安心して受験させたいという親心なのでは」と話している。
■ ■

スイートルームを利用した「自習室」。
隣にはソファでくつろげるスペースもある
東京・新宿の京王プラザホテルで、同ホテル提供
■ ■
私が受験生だった時に泊まった宿は、
現役の時、弘前:駅前のカネサダ旅館。
一浪の時、栃木県の旅館。
いずれも、大学指定の旅館組合が斡旋してくれた旅館でした。
■ ■
弘前へ行くのも、栃木県へ行くのも、JR(当時の国鉄)と青函連絡船で行きました。
東京へ行くのは、スカイメイトで飛行機が主流でしたが、弘前と栃木は、列車が便利でした。
ちなみに高校の修学旅行(京都)も国鉄の夜行寝台急行でした。
■ ■
弘前へは、西高の仲間と行きました。
全員、一期校を‘落ちた’同級生でした。
私が医学部、他に農学部と教育学部が一人ずつでした。
農学部を受けた、友人だけが合格しました。
彼とは、今でも親友です。
■ ■
二期校の受験でしたから、気は楽でした。
修学旅行気分で行った記憶があります。
帰りは、函館でお鮨を食べて帰ってきました。
函館から、夜行寝台で帰って来たのを覚えています。
■ ■
栃木県へ行ったのは、自治医大の二次試験でした。
北海道からの受験生が、まとまって一つの旅館に宿泊しました。
この時は、まだ一期校の合格発表前でした。
北大を受けた人と、札幌医大を受けた人がいました。
自己紹介をして、仲良く、宿泊した記憶があります。
栃木に行ったのは、はじめてでした。
都会を想像して行ったのですが、思っていたより、ずっと田舎だった記憶があります。
■ ■
申し訳ないことに、自治医大からは合格通知をいただきましたが、結局、札幌医大に入学しました。
もし自治医大に行っていたら、今は違う仕事をしていたと思います。
同じ旅館に泊まって、相部屋でした。
たった2日間でしたが、同宿できてよかったと思っています。
■ ■
今は、旅館で相部屋なんて考えられないでしょうが、案外リラックスできてよかったものです。
もし、北大や札幌医大の受験で札幌へいらっしゃるのでしたら、
試験場の近くにある、ビジネスホテルもよいと思います。
北大正門前には、東横イン、札幌駅西口北大前があります。
高級ホテルは、防犯、防音(安いホテルは隣室の音が気になることがあります)の面で優れています。
会場に近いホテルは、なんと言っても、便利です。
受験生の皆さんのご健闘を祈念しています!
医学講座
看護師の喫煙
平成20年1月19日、北海道新聞朝刊の記事です。
禁煙訴えているけど
看護師3割「吸ってます」
道看護協会調査 職場でストレス
■ ■
道内で働く看護師のうちたばこを吸う喫煙者の割合が30%に上り、道内の女性平均を大幅に上回ることが道看護協会の調べで分かった。
職場のストレスなどが背景にあるとみられるが、医療機関は禁煙を訴えているだけに、関係者は「もっと自覚を」と呼びかけている。
■ ■
調査は昨年8月に、同協会の全会員約3万7千人を対象に行い、約3万8百人から回答があった。
回答率は83%で、回答者の95%が女性だった。
2004年にも約6千人を対象に喫煙率調査をしているが、全会員を対象にしたのは初めて。
■ ■
アンケートでは、たばこを「吸っている」が30%だったのに対し、「吸わない」は55%、「吸っていたがやめた」は15%だった。
喫煙者の割合は、2007年に全国九地域の中でワーストだった道内女性の19%(日本たばこ産業調べ)を大きく上回り、全国の看護師の20%(2006年)と比べても飛び抜けていた。
また稚内40%、根室35%など、地方都市で高い傾向があった。
■ ■
どんな時にたばこを吸いたくなるかの問いには、
「イライラした時」が68%、
「酒を飲んだ時」が63%、
「気分転換したい時」が59%と多かった。
そのほか
「緊張を和らげたい時」(30%)、
「憂うつや不安を忘れたい時」(21%)など。
■ ■
喫煙率の高さについて、同協会の高橋慶子常任理事は
「命にかかわる仕事の緊張感や対人関係で、ストレスがかかる職場なのが影響しているのでは」と話す。
ただ、医療界はたばこの健康被害を訴えてきただけに、
「看護職の喫煙率が高くては患者さんに示しがつかない」と頭を抱える。
■ ■
同協会は2002年に「たばこ対策委員会」を設置。
2004年の調査で35%だった喫煙率の半減を目指し、
啓発ポスターの作製や禁煙を推進するリーダーを育成するための講習会などを行ってきたが、今回は5ポイントの減少にとどまった。
道外では受験資格に「非喫煙者」を条件とする看護学校もある。
■ ■
日本禁煙学会(東京)の理事を務める深川市立病院の松崎道幸主任医長は
「周りに喫煙者が多いから『吸ってもいいや』という意識もあるのでは」と分析。
「分煙ではなく、病院が敷地内禁煙に取り組み、吸えない環境をつくっていくことが大切」と話している。

以上、北海道新聞より引用
■ ■
看護師さんに喫煙者が多いのは昔からです。
多くの病院でナース・ステーションの横に、休憩室がありました。
昔は、そこでタバコが吸い放題でした。
私の記憶では、大学病院と市立札幌病院以外は、ナース・ステーションの横で‘先生’もよく吸っていました。
■ ■
時代は変わって、今や敷地内禁煙が主流となりました。
敷地内禁煙になっていないと、禁煙指導をしても、料金がいただけないという‘事情’もあります。
ある‘先生’が、病院でタバコが吸えないなんて、オレに辞めろと言うに等しいと…
言ったとか言わないとか…
結局、その先生はお辞めになって開業なさったそうです。
■ ■
私が、禁煙をすすめる一番の理由は、健康上の問題です。
お肌にも、キズの治りにもよくありません。
タバコには多くの発癌物質が含まれています。
毎日、発癌物質を口からノド→肺まで、塗りつけているようなものです。
■ ■
私は、耳鼻科の先生と一緒に、たくさんのガン患者さんの手術をしました。
口の奥を、咽頭(イントウ)といいます。
カゼをひくと痛くなるところです。
ここにガンができると、手術や放射線、抗癌剤で治療をします。
■ ■
カゼをひいてノドが痛いだけでも、苦痛です。
ここに、ガンができららどんなに苦しいでしょうか?
声帯にガンができると(下咽頭癌カイントウガンといいます)、声が出なくなります。
可愛い声が、ガラガラ声になります。
手術で声帯を取ってしまうと、二度と同じ可愛い声が出せなくなります。
■ ■
食べ物も食べられなくなります。
1月9日の日記に書いたように、首に穴が開いてしまう人もいます。
悲惨な結果になる前に、タバコはおやめになるべきです。
私から、喫煙者の皆様への‘ご忠告’です。
未分類
センター試験前日
大学入試センター試験が明日から、2日間の日程で開催されます。
札幌でも、北大や河合塾札幌校などで行われます。
私が、昭和49年(1974年)に札幌医大を受験した時は、桑園予備校という予備校で試験がありました。
医学部の教室は、階段教室になっているため、前の人の答案が見えることがあります。
そのため、入学試験は予備校を借りて行われていました。
■ ■
桑園予備校は、今はもうなくなってしまいました。
今は、札幌情報未来専門学校という専門学校になっているようです。
札幌市中央区北5条西13丁目に、校舎はまだ残っています。
近くを通ると、予備校や試験のことを思い出します。
■ ■
何歳になっても、試験はイヤなものです。
信じられないかもしれませんが、私は50歳になっても
『アッ!ヤバイ!』
『明日試験なのに、何も勉強していない!』
という‘悪夢’をみていました。
■ ■
不思議なことに、大学の教員になって、こちらが試験問題を作成する側になってからも、この‘悪夢’にうなされました。
『アッ!問題を作る側だった!』
と気づいて目が覚めたこともありました。
■ ■
センター試験は、国公私立の大学教員などを中心とした約400人が問題を作成しているそうです。
委員の任期は2年で、毎年約半数ずつ交代します。
おそらく、国立大学教員で、大学入試の試験問題作成を、専門に‘研究’している‘先生’はいないと思います。
試験問題を一番よく研究し、勉強しているのは、予備校の‘先生’です。
■ ■
大学教員にとって、試験問題作成は、辛い仕事です。
‘良い問題’を作るのは、本当に至難のわざです。
センター試験が、過去の良問を出題する方針を出したのも、ネタ切れになったからです。
20年近くも試験を続けていると、良い問題は出つくしてしまいます。
予備校の模擬試験にも気を遣います。
■ ■
試験前日は、緊張します。
体調を崩す人も出てきます。
ちょっと位の熱でしたら平気です。
ただ、カゼ薬には注意してください。
眠くなる薬があります。
バスの運転手さんが気を失った事故もあった位です。
■ ■
試験当日は、誰でも緊張するものです。
一年間の努力は必ず報われます。
マークシートの欄を間違えないように。
解答用紙のマークシートに受験番号をマークし忘れる人がいるそうです。
自分が緊張している時は、他人も緊張しています。
緊張して眠れなければ、黙って目を閉じているだけでも大丈夫です。
明日から2日間、体調に気をつけて頑張ってください。
応援しています♪
医療問題
再診料引き下げ
平成20年1月17日、朝日新聞朝刊の記事です。
再診料下げ医師会反発
医師不足緩和-増す不透明感
開業医の収人源にどこまで切り込み、勤務医不足対策に回すことができるのか-。
診療報酬の2008年度改定の配分をめぐる議論が、16日の中央社会保険医療協議会(中医協)で始まった。
厚生労働省は、勤務医に比べて優遇されている開業医の再診料の引き下げを提案したが、日本医師会は猛反発。対立が続いた。
対策の実現に向けて不透明感が増している。(太田啓之)
■ ■
対馬忠明・健康保険組合連合会専務理事
開業医の再診料の引き下げた分を産科や小児科につけるのが、医師不足対策の分かりやすいメッセージとなる。
鈴木満・日本医師会常任理事
開業医が楽してもうけているなんてことはない。引き下げは絶対反対だ。
■ ■
都内で聞かれた中医協の会合。
健保連などの支払い側と医師会の激しい応酬は予定を1時間オーバーし、3時間に及んだ。
外来の初診料は、開業医、勤務医とも2,700円で同額だが、再診料は勤務医570円に対し、開業医は710円。
患者は自己負担が少なくて済む病院に通いがちとなり、入院患者の治療が本来の仕事であるはずの勤務医は外来に追われ過剰労働を強いられている。
このため、厚労省は今回の診療報酬改定の「緊急課題」として、開業医の再診料の引き下げを提案した。
昨年末の改定率交渉では、医師の収入に直結する診療報酬の「本体部分」について、8年ぶりに0.38%引き上げることが決定。
この財源に加えて、再診料引き下げで浮いたお金を、勤務医不足が著しい産科・小児科などに重点配分する方針を打ち出した。
■ ■
支払い側も厚労省に歩調を合わせる。
健保組合は昨年末の2008年度予算編成で、中小企業向けの政府管掌健康保険への国の負担を、共済組合と合わせ1千億円肩代わりすることをのまされた。
社会保障費の歳出削減を健保組合などの「犠牲」で達成し、診療報酬のマイナス改定を回避した。
これで開業医の既得権益が温存されるなら、我々は『取られ損』(健保連幹部)との思いが強い。
■ ■
医師会の鼻息は荒い。年明け早々、「再診料は医師の無形の技術を評価する重要な項目で、死守する」との方針を決定。
医師不足対策としてプラス改定分に相当する国費300億円(医療費べースで1,200億円)をあてることは認めているが、
再診料という自らの懐には「手をつけさせない」という考えだ。
■ ■
次期総選挙がとりざたされるなか、支持をとりつけたい自民党も医師会をバックアップ。
厚労関係議員は「医師会には思い切りけんかするよう言ってある。
再診料を引き下げる必要など、まったくない」と話す。
■ ■
中医協は2月中旬までに再診料をはじめとする個別の治療行為の価格を決定するが、調整難航は必至だ。
医師会の利害むき出しの主張に、他の委員が「それでは国民の納得が得られませんよ」と、半ばあきれ顔で諭す場面もあった。
■ ■
開業医への報酬手厚さはっきり
厚労省の昨年6月の調査によると、病院の1ヵ月当たりの赤字額は2年前の前回調査に比べて2倍以上の1,315万円に膨らむ一方、
開業医の平均の黒字額は100万円増の336万円。
平均年収も私立病院の勤務医が1,603万円に対し、開業医は2,531万円。
■ ■
再診料や慢性疾患の管理料など、開業医への報酬の手厚さは、数字にはっきりと表れている。
一方、勤務医が担う高度な手術や病院の設備投資に対する報酬は概して低い。
開業医の権益が温存され、診療報酬の配分の偏りがただされなければ、
病院が行う「命にかかわる医療」の質が下がる恐れがあるとの指摘も出ている。
■ ■
2008年度の診療報酬改定の骨子案
↑主な引き上げ項目
産科、小児科の重点評価
開業医の夜間診療の報酬を引き上げて時間外診察を促し、勤務医の救急医療負担を軽減
重症患者の専門的・総合的医療を担う大病院の入院料上乗せ
放射線治療や緩和ケアなどがん治療の体制が整った施設を評価
■ ■
↓主な引き下げ頂目
開業医の再診料をカット
療養病床の入院料を引き下げ、介護保険施設への転換を促進
軽いやけどなど、簡単な治療への評価を廃止
コンタクトレンズ専門の診療所への報酬をカット
(以上、朝日新聞より引用)
■ ■
朝日新聞の他、読売新聞などでも、同じ論調で‘医師会批判’‘開業医批判’が出ています。
私は、再診料の710円と570円の差ではないと思います。
患者側が支払うのは、3割負担の方で、710円の3割→210円。
570円の3割→170円です。
特売のティッシュを買うのでしたら、210円が170円で売っていれば、間違いなく買いに行きます。
ところが、一ヵ月に一回行く、美容室の料金だったとします。
210円-170円=40円です。
40円の違いで、美容室を変えますか?
■ ■
70歳以上の高齢者の方でしたら、もっと違いが少なくなります。
710円の1割→70円。
570円の1割→60円です。
70円-60円=10円です。
たった10円の違いで、3時間待ちの3分診療と言われる、大病院へ行きますか?
大部分の方は、大病院の方が、なんとなく安心できるから、大病院へ行かれるのです。
もう少し、詳しい方は、大病院が安い理由をちゃんとご存知です。
■ ■
開業医が‘儲かる仕組み’は、再診料の違いではないのです。
特定疾患療養管理料(月2回まで)
診療所 225点
病床数99床以下病院 147点
病床数100~199床病院 87点
という、管理料が‘開業医儲かりの秘密です’
大病院はこれがないので‘安い’のです。
■ ■
・悪性新生物 (ガン)
・糖尿病
・高血圧性疾患
・虚血性心疾患
・不整脈
・心不全
・脳血管疾患
・単純性慢性気管支炎
・詳細不明の慢性気管支炎
・肺気腫
・喘息
・胃潰瘍
・十二指腸潰瘍
・胃炎及び十二指腸炎
・慢性ウイルス肝炎
・アルコール性慢性膵炎
・その他の慢性膵炎
などの病気で通院している患者様に、「計画的な療養上の管理を行った場合」に、月2回を限度に請求できると定められています。
これが、高いのです。
診療所 225点ということは、2,250円です。
再診料の他に請求できます。
再診料710円+特定疾患療養管理料2,250円=2,960円。
この他に、処方箋料などがかかります。
■ ■
私たちのような、形成外科には特定疾患療養管理料がありません。
ケロイドなど、難治性の病気や、
生まれつきの病気(唇裂など)に、一人当たり一時間かけて説明しても
再診料しか請求できません。
■ ■
開業医の平均年収が2,531万円と書かれています。
ただ、ここから借金を返済しなくてはなりません。
退職金もありません。
私のように、深夜までメールの返事を書いて、
朝から夜まで働いても、そんなに‘儲かる仕事’ではありません。
■ ■
自分が働いて、一人でも多くの方に喜んでいただいて…
自分の好きな仕事ができる喜びがあるから、仕事を続けています。
マスコミの方も、もう少し突っ込んで、開業医批判をなさっていただきたいと思います。
私たちのような形成外科では、‘再診’は、赤字部門です。
人件費・医薬品費・材料費・光熱費・減価償却費などを考えると、、‘再診’は、赤字になります。
昔の記憶
経歴詐称
昨日、お問い合わせをいただいた、女性の方です。
院長日記を読んで、よさそうな先生だと思ったけれど、
昭和55年に札幌医大を卒業して、1980年(昭和55年)北大医学部形成外科と書いてあった。
札幌医大を卒業した先生が、北大に入るわけがない!
経歴詐称じゃないか!
というお怒りのお電話でした。
担当した職員が驚いていました。
■ ■
経歴詐称はしておりません。
確かに、札幌医大を卒業して、北大に行く学生が少なかったのは事実です。
私の同期では、4人でした。
私:北大形成外科。
森川清志先生:北大第一内科。
森川玲子(旧姓:小林玲子)先生:北大皮膚科。
橋本洋一先生:北大神経内科、北大免疫研究所。
■ ■
今は、医科大学や医学部を卒業し、医師免許を取得すると、2年間の臨床研修が義務付けられています。
私の頃には、大部分は、大学の医局に‘入局’しました。
大学医局というのは、教授を頂点とする、医師の集団です。
古き、よき時代でもあり、悪しき点も、あったのが医局でした。
幸い、私が入った、北大形成外科は家庭的なあたたかさのある、よいところでした。
■ ■
大学の医局に入らないで、大きな病院へ就職する仲間もいました。
脳神経外科を選んだのは、同期では6人いましたが、札幌医大の脳神経外科へ入局したのは一人でした。
一番多かったのが、中村脳神経外科病院でした。
中村脳神経外科へは3人が就職しました。
勤医協病院という病院へ就職した仲間もいました。
■ ■
医師は大学を卒業して、医師免許証をいただいただけでは何もできません。
自動車学校でいうと、仮免許取得程度です。
路上に出て、横に教官に乗っていただいて、いつでも非常ブレーキを踏める状態で、トレーニングを受けます。
仮免許で、乗せられる‘患者様’は、たまったものじゃありませんが、これが日本の現状です。
■ ■
中には、ロクに路上教習も受けないで、いきなり高速道路を飛ばすような‘先生’もいます。
自動車の運転もそうですが、
最初に運転を教えてくれた‘先生’のクセが、その人の運転に影響を及ぼします。
丁寧に慎重に運転するクセがついた人は事故率が低いそうです。
■ ■
弁護士の高橋智先生が、弁護士も最初についた‘先生’によって、大きく影響を受けると何かに書かれていました。
医師も、最初に、見て・聴いて・覚えた、やり方が、その‘先生’に影響を与えます。
三つ子の魂(タマシイ)というヤツです。
■ ■
私が形成外科を専攻しようと思った当時は、札幌医大には形成外科がありませんでした。
口腔外科の、篠崎文彦先生がクラブの先輩だったので相談しました。
東京に行く手もあるが、北大へ行ったらどうだ、と篠崎先生から、アドバイスをいただきました。
■ ■
北大形成外科には、私より先に、
松本敏明先生(札幌医大22期、昭和50年卒)
大岩 彰先生(札幌医大26期、昭和54年卒)
のお二人の札幌医大の先輩がいらっしゃいました。
私は、最終的に、松本敏明先生から、入局お誘いの電話を受けて、北大に決めました。
昭和55年1月のことでした。
同期ではかなり遅い方でした。
■ ■
こうして、私は、札幌医大から北大へ行きました。
北大の同期では
浅見謙二先生(北大51期、昭和50年卒)、小児科を経験し、形成外科へ転科。
井川浩晴先生(北大56期、昭和55年卒)。
斉川雅久先生(北大56期、昭和55年卒)。
菅野弘之先生(北大56期、昭和55年卒)。
私。
の合計5人が、昭和55年4月に、北大形成外科へ入局しました。
私たちの、新人歓迎会は、中島公園の大手門という店で行っていただきました。
大浦武彦教授が、5人も入局してくれて感慨深いものがあると、お言葉を述べられたのを記憶しています。
■ ■

1980年北大形成外科入局当時
私、二期上の小椋哲実先生、同期の井川浩晴先生
北大病院6-3病棟ドクタールームで