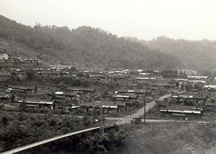医療問題
電子カルテ
医療法という法律で、
カルテは5年間の保存義務があります。
大学病院などでは、
何十年分ものカルテを保管しています。
その保管場所や管理が大変です。
北大形成外科に勤務していた時は、
古い外来棟にカルテがありました。
手術記録などを調べるために、
カルテ探しを何度もしました。
■ ■
カルテの保管場所は
掃除をしていませんでした。
古いカルテを探しに行くと、
必ず、鼻の中が真っ黒になりました。
もちろん、手も真っ黒。
白衣は汚れてもいいような、
古い白衣を着て行きました。
当時の北大には、
診療情報管理士の方は
いらっしゃらなかったと思います。
■ ■
これからは電子カルテの時代だと思います。
航空券の予約・発券もネットでできる時代。
チケットはなくなり、
携帯電話やカードで、
‘ピッ…’とするだけで、
搭乗ができるようになりました。
医療機関は、
残念ながら…
一番IT化が遅れている業種の一つです。
■ ■
私たちが電子カルテの導入で、
一番困るのが、
過去のカルテを参照することです。
昨年の朝日新聞の投稿には、
韓国の先進的な病院を訪問する機会があった。
そこでは1958年の開院以来、
過去の入院診療録約100万件を
すべてデジタル化して保存しており、
診療録管理室には約50人のスタッフが配属されていた。
とありました。
■ ■
これは実にすごいことです。
電子カルテの導入費用以上に、
過去の100万件の入力費用がかかります。
札幌市内の総合病院で、
電子カルテが導入されました。
担当の先生が、
過去のカルテはどうやって見るのですか?
と聞いたところ…
『過去カルテの電子化は、
予算に入っていません』
とあっさり言われたそうです。
■ ■
私が勤務医をしていた時代に、
各病院にコンピューターシステムが入りました。
毎日、快適に動いていたのではありません。
システム障害が発生すると、
院内放送で、
『ただいま、システム障害が発生しています』
『復旧の見通しは立っていません』
『各部署では、手書き対応に変更してください』
という
悪夢の放送が流れました。
■ ■
外来は私と看護師さんが一人だけ。
患者さんには…
『ごめんなさい』
『今日、お薬を出すと、何時になるかわかりません』
『申し訳ありませんが、次にしてください』
『わかりました、先生も大変ですね』
なんてことがありました。
■ ■
札幌美容形成外科でも
電子カルテの導入を検討しています。
今の電子カルテはかなり進歩したようです。
過去カルテ入力など、
難問がありますが、
なんとか早期に導入しようと考えています。
システム障害になっても、
お薬は出せるように準備します。
昔の記憶
防災の日
今日は防災の日です。
私自身は災害の被害を
受けたことはありません。
ただ忘れられないのが、
札幌医大の学生だった時に経験した
有珠山の噴火でした。
■ ■
札幌医大第二内科では、
洞爺湖近くの壮瞥町(そうべつちょう)の
集団検診を実施していました。
壮瞥町(そうべつちょう)は、
横綱北の湖の出身地です。
小畑敏満(おばたとしみつ)さんが本名です。
私たち学生は、
第二内科が募集した
集団検診の学生アルバイトとして
検診のお手伝いをしていました。
■ ■
壮瞥町役場近くの旅館に宿泊して、
早朝から壮瞥町内の検診場所へ行き、
採血や心電図の準備などをしていました。
なかなか楽しいアルバイトで、
そのバイトをきっかけにして
第二内科に入局し、
循環器内科医となった友人も
たくさんいました。
北の湖のご両親も
検診にいらしたのを記憶しています。
■ ■
噴火があった時、
私は旅館の風呂に入っていました。
同級生が、
『本間、山が噴火したぞ!』
『窓から見えるから見てみろ!』
というので、
風呂の窓を開けて見たのを覚えています。
最初は青空に…
きのこ雲ができて…
‘すっげぇ~!’
てな、感じで眺めていました。
■ ■
すごい!と感動したのは、
最初のうちだけでした。
きのこ雲はみるみるうちに…
空全体に広がり…
あっという間に青空がなくなり、
夜のように真っ暗になりました。
真っ暗になったのが先か?
その後かは覚えていません。
稲妻が走り、
雷がゴロゴロごろごろと
大きな音を出したかと思うと、
あっという間に…
泥の大雨が降ってきました。
■ ■
『窓を閉めろ~!』
誰かが叫んだように思います。
旅館の屋根が抜けるか?
と思うほどの泥の大雨でした。
道路も通行止め。
避難しようにも、外へ出られません。
本当に怖い思いをしました。
幸いなことに、
ケガはありませんでした。
■ ■
それからしばらくは、
集団検診は中止となり、
私たち学生も、
道路にたまった火山灰の除去作業を
お手伝いしました。
一度しか経験したことがない、
火山の噴火ですが、
もう二度と体験したくはありません。
自然の驚異は恐ろしいものです。

札幌医大の学生だった時
後方に見えるのが有珠山
噴火はこの後で起こりました
昔の記憶
高校進学
私は大夕張の鹿島中学校を、
昭和45年に卒業しました。
当時の夕張市には、
北炭、三菱という炭鉱会社があり、
今よりずっと栄えていました。
私が住んでいた大夕張にも、
中学校が1校、高校が1校ありました。
今は何もありません。
ダムの底に沈むのを待っています。
■ ■
中学校は一クラス40人程度で、
A組からG組までの7クラスがありました。
大部分の生徒は、
地元の高校へ進学しましたが、
北海道内の進学校である、
函館ラサール高校(男子校)や
札幌市内の公立高校、
夕張市内でも大学進学率が高い、
夕張北高へ進学する生徒もいました。
■ ■
私の鹿島中学の先輩に
Sさんという男子がいました。
とても勉強ができました。
Sさんは、鹿島中学校から、
札幌南高に進学し、
東大文Ⅰに現役合格しました。
私たちの間では、
‘郷土の英雄’でした。
Sさんは、
その後、国家公務員上級試験を通り、
官僚になられたと聞いています。
■ ■
私たちの世代は、
一生懸命勉強をして、
‘いい高校’から
‘いい大学’へ進学することが、
‘いい子ども’の条件だったように思います。
親もそれを願って、
経済的に苦しくても、
子どもを札幌や函館の進学校へ出しました。
それが親にとっての
喜びだったようにも思います。
■ ■
私が札幌西高校を卒業したのが
昭和48年(1973年)3月でした。
私は現役で札幌医大を落ちました。
大夕張の鹿島中学校から
函館ラサール高校へ行った友人も、
北大を落ちました。
同じく大夕張から札幌北高へ進学した友人も、
北大を落ちました。
■ ■
夕張から札幌と函館の進学校へ行った、
私たち3人は
全員第一志望の大学を落ちました。
昭和45年に
鹿島中学校を卒業した生徒のうち、
ただ一人北大に現役合格したのが、
大夕張で地元の夕張東高へ進学した
I君でした。
夕張北高に進学したT君も
小樽商大に現役合格しました。
■ ■
夕張から外の高校へ出た3人(私も含めて)が
高校時代に勉強をサボったのではありません。
おそらく夕張に残ったI君やT君が
一生懸命、勉強したのだと思います。
私は自分が卒業した、
札幌西高が好きですし、
札幌に出てきてよかったと思っています。
■ ■
私たちの世代のエリートは、
北大法学部や小樽商大という
道内の難関大学を卒業して、
北海道拓殖銀行に入行しました。
‘拓銀に入ったんだってねぇ~’
‘すごいねぇ~’
‘勉強できたからねぇ~’
というコースでした。
ところが、拓銀は経営破たん。
人生なんてわからないものです。
■ ■
私は、人間は目標へ向かって
努力している間が、
一番、夢があって充実していると思います。
その時は気づかないけれど…。
私も高校時代に、
ボロ家で…
勉強ができなくて…
成績が上がらなくて…
苦しんでいた時代があって
よかったと思っています。
自分が苦しんだ経験が、
役に立っていると思います。

中学3年の修学旅行
層雲峡にて(中央が私)
下唇が出ていると言われ
気にして下唇を噛んでいます
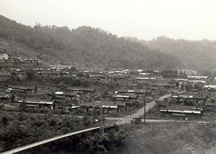
鹿島中学校があった
夕張市鹿島常盤町
手前はつり橋です
昔の記憶
私が住んだ家
私が子供の頃は、
父親が勤務していた病院の社宅に住んでいました。
生まれてから、小学校2年生までは、
札幌郡手稲町字金山。
小学校3年生から中学校1年生までは、
美唄市茶志内町日東(ビバイシチャシナイチョウニットウ)。
中学校3年間は、
夕張市鹿島(ユウバリシカシマ)、通称大夕張(オオユウバリ)。
高校1年生から、札幌市西区八軒(ハチケン)でした。
■ ■
西区八軒の家だけが、父の所有でした。
お金がなかったので、土地は長い間借地でした。
昭和30年代に建てられ、
昭和36年に購入した、中古の建売木造住宅でした。
最初は、父の両親と弟妹が住んでいました。
私が札幌西高校へ入学したため、
父の母親(私の祖母)が住んでいた家に住みました。
当時は、こうして地方から札幌へ出てくる高校生がいました。
■ ■
お世辞にも、立派な家とは言えませんでした。
トイレは水洗式ではありません。
私の家は、
七畳くらいの一部屋に、
私と弟と母親が
寝泊りしているような家でした。
壁が汚かったので、
ペンキを買ってきて自分たちで塗りました。
床は父親がフローリングを自分で貼りました。
■ ■
高校時代、同級生に、
『今度、本間の家(ホンマンチ)へ行ってもいぃ?』
と言われるのが一番困りました。
見栄を張っていたのではありませんが、
友人に来てもらうような家ではありませんでした。
友人の家は、
西区西野の閑静な住宅地にあり、
新築の立派な家でした。
■ ■
私は、あまり贅沢はしません。
着るものも、食べものも。
ただ、家にはこだわりがあります。
これは、高校生の頃に、
ビンボーな家に住んでいたためだと思います。
マンションや不動産の広告は好きなのでよく見ます。
自分ではじめて新築した家は、
張り切りすぎて、住宅ローン地獄になりました。
米国のサブプライムローン問題がよく理解できます。
■ ■
自分がコンプレックスを持ったことには、
こだわりができるようです。
私は、高校生の時に、
自分も友だちの家のように…
いつかは新築の立派な家に住みたい。
と考えるようになったのだと思います。
私は土をいじるのが好きですが、
家の壁のクロスなどを補修するのも好きです。
自分が住んでいる家はキレイに大切にしています。
昔の記憶
ペット可の貸家
平成6年は、
今のように
ネットが発達していませんでした。
帯広に転勤する時は、
家を探すのに苦労しました。
愛犬のチェリーを飼っていたので、
『犬を飼ってもOK』
という貸家を探すだけで大変でした。
帯広の職業別電話帳を、
NTTでコピーして、
札幌から片っ端から電話をしました。
■ ■
帯広の不動産屋さんの中には、
『イヌを飼ってもいいなんて大家さんはいませんよ!』
とピシャリと言われたところもありました。
ようやく何軒か目星をつけて、
家内と帯広へ車で向かいました。
12月10日の吹雪の日でした。
夕張を過ぎた頃には、
前方が雪で見えなくなり…
このまま遭難するのでは?
と思いました。
■ ■
やっとの思いで、帯広に着きました。
これは!
と思っていた家は、×でした。
最後にたどり着いた家は、
不動産屋さんが終了してしまっていました。
FAXしていただいた資料から
その家を見に行きました。
■ ■
外から家の中を見ると、
明かりが点いていました。
家内と、
おそるおそるピンポンを押してみました。
そこのお宅の奥様が出てきてくださいました。
『私たちも貸家探しで苦労したのょ。』と
とても親切に応対してくださいまいした。
その奥様から、
大家さんは
大手住宅建材メーカーにお勤めであること。
札幌に転勤で住んでいらっしゃること。
住所と電話番号も教えていただきました。
■ ■
札幌の大家さんのご自宅は、
私が住んでいたのと同じ、
西区山の手にありました。
お電話をして、
家内とチェリーを連れてお伺いしました。
『この犬を飼ってもいい家が見つからないと、
私は帯広厚生病院に赴任できません。』
万一、犬が住宅を毀損(キソン)した時は、
すべてこちらが費用を負担して直します。
必死の思いで、お願いしました。
■ ■
大家さんは、快く許可をくださいました。
こうして、
私は帯広厚生病院へ赴任できることになりました。
今でこそ、
ペット可のマンションや住宅が増えています。
14年前は、
まだペット可の家はありませんでした。
その後、私は札幌の自宅を貸しました。
もちろん『ペット可』です。
■ ■
平成元年に、
分不相応な家を建てて、
住宅ローン地獄に陥っていた私は、
平成7年1月に帯広に転勤して、
自分の家を借りていただき、
ローン地獄から
脱出することができました。
世の中何が幸いするかわかりません。
今でも家を貸してくださった
大家さんに感謝してます。

帯広でお借りした家
平成7年4月16日
昔の記憶
帯広への転勤
昨日も書きましたが、
私は平成7年1月1日付けで、
JA帯広厚生病院へ赴任を命じられました。
北大形成外科の人事異動です。
人事異動とは言っても、
前任の市立札幌病院は、
自己都合退職。
『一身上の都合により…退職を…』
という辞表を出して退職しました。
正直なところ…
退職したくはありませんでしたが、
これが、医者社会の掟(おきて)でした。
■ ■
せっかく家も建てて、
子どもたちも、
学校を変わりたくないと言っている。
『お父さん一人で単身赴任してちょうだい!』
と家内と喧嘩になりました。
嫌がる家族を巻き込んで…
正月早々、
夜逃げのような引越しでした。
■ ■
お世話になった
市立札幌病院の婦長さんが、
『先生、帯広は寒いから…』
とカシミアのマフラーを
プレゼントしてくださいました。
マフラーも素敵でしたが、
その心が、嬉しくて、
そのカシミアのマフラーは
今でも大切に使っています。
■ ■
平成6年12月10日土曜日に、
北大形成外科の忘年会を欠席して、
早朝5時に札幌の家を出て、
帯広まで家探しに行きました。
その日は天候が悪く、
途中から猛吹雪になりました。
札幌→帯広の道にも
慣れていませんでした。
■ ■
日高の山を越えると、
十勝平野は晴れていました。
十勝地方は氷点下30度近くまで
冷え込むことがある寒い土地です。
太平洋側にあるので
積雪量は日本海側の札幌と比較すると
少ないのが特徴です。
どこまでも続く、
広大な畑が十勝地方の特徴です。
■ ■
帯広は、確かに寒いのですが、
冬でも晴れた日が多く、
札幌に比較すると、
お日様が輝いていました。
家族はイヤイヤ付いて来たのですが、
子どもたちはスケートを覚えたり、
夏は釣りをしたり…
夜空には満天の星があり…
帯広での生活を楽しんで暮らしました。
■ ■
帯広厚生病院は立派な病院でした。
JA北海道厚生連の中でも、
トップクラスの黒字病院でした。
市立札幌病院では、
買ってもらえなかった…
ドイツ製の手術用顕微鏡も、
ポンと買っていただけました。
仕事は…
‘超’忙しかったのですが、
充実した毎日でした。
40歳から43歳までの、
3年間勤務しました。
院長の休日
カーナビ2008年問題
私は13年前の、
1995年(平成7年)1月1日付けで、
JA帯広厚生病院形成外科
主任医長として赴任しました。
帯広は、食べ物が安くて美味しく、
住みやすい街でした。
ただ一つだけ困ったのが、
夜道の運転でした。
■ ■
十勝地方は道路も整備されていて、
農道でも立派に舗装されていました。
ある夜に、帯広空港から帰る途中で、
道に迷いました。
前の車について走っていて、
いつもと違う道へ
迷い込んでしまいました。
土地勘がないところで、
畑の真ん中で…
自分が今、
どちらに向いているのかも…
わかりませんでした。
■ ■
今でしたら携帯にもGPSがついています。
当時は磁石も持っていません。
冬だったので、道路標識もわかりません。
ようやくの思いで、家に帰りました。
道に迷ったおかげで、
私はカーナビを購入しました。
12年前のカーナビがまだ活躍しています。
■ ■
そのカーナビが、
8月下旬から位置がずれるようになりました。
何回か調節して、
位置異常を直してもすぐに戻りました。
10年以上も使ったのだから…
壊れても仕方がないね。
と諦めていました。
■ ■
新しいカーナビを購入しようか?
とkakaku.com
を検索していたところ…
偶然、2008年問題というのを
見つけました。
GPSの耐用年数が
2008年8月17日で切れるので
古いカーナビは位置異常を起こすのだそうです。
■ ■
kakaku.comのおかげで
今日、カーナビを無償修理していただきました。
正常になるまで、
4日程度かかるそうですが、
これでまたしばらく使えそうです。
地図データーは古くなっていますが、
位置は正確なのでまだ使えます。
同じような症状が出ている方は、
メーカーにお問い合わせください。
未分類
北京オリンピックの少女
北京オリンピック開会式に
赤い服を着た、
可愛い少女が出ていました。
朝日新聞の記事です。
少女の歌声は「口パク」
五輪開会式、舞台裏に別の子
2008年8月13日0時15分
開会式でソロで歌い、
「天使の歌声」と人気を集めていた林妙可ちゃん(9)が、
実は「口パク」だったことを音楽総監督の陳其鋼氏が
中国の通信社、中国新聞社の取材に告白した。
舞台裏で別の女の子が歌っていたという。
インターネット上では
「純粋な子どもにうそをつかせるのはよくない」
と批判が出始めた。
■ ■
陳氏によると、
楊沛宜ちゃん(7)という別の子の歌声だった。
選考の際、沛宜ちゃんの歌声が一番よかったが、
見た目がよりかわいらしい妙可ちゃんが
舞台に出ることになったという。
陳氏は
「対外的なイメージと国益を考えて採用した方法だ」
と説明した。
沛宜ちゃんは
「歌声だけでも披露できて満足、悔しくはない」。
ネット上の批判は、
当局が次々と削除している。(峯村健司)
(以上、朝日新聞より引用)
■ ■
北海道新聞には次の記事が掲載されました。
歌った少女は「傷心」
五輪開会式の“口パク”(2008年8月23日 22:41)
【北京23日共同】
北京五輪開会式の“口パク”問題で、
実際に革命歌曲を歌った少女、
楊沛宜さん(7)について、
担任の教師が23日までに、
自身のブログで
「がっかりし、傷ついているようだ」
と近況を伝え、
「楊さんを二度と傷つけないでほしい」と訴えた。
■ ■
教師によると、
楊さんは18日に
口パクをした林妙可さん(9)が
出演した娯楽番組を興奮した様子で見た。
しかし、
司会者が、実際には楊さんが歌ったことを紹介しなかったため、
がっかりした表情を浮かべ、
ひと言も口をきかずに就寝。
翌朝、
楊さんが歯形が残るほど強く
自身の腕をかんでいたのを家族がみつけた。
■ ■
両親はメディアの取材から守るためとして、
楊さんを「遠く」に移したという。
教師は、
楊さんが林さんを含め
一緒に開会式の練習をした子どもたちに
会いたがっているとしている。
(以上、北海道新聞より引用)
■ ■
私は開会式をTVで見た時に
中国にも可愛い女の子がいるなぁ~
と思いました。
また、中国人が可愛いと感じる
女の子が、二重まぶたで…
パッチリとした目の子なんだなぁ~
と思いました。
■ ■
私は2002年に上海で行われた
国際美容外科学会に参加しました。
香港の学会には、
1998年に一度行っていましたが、
上海ははじめてでした。
そこの第九人民病院というところで、
ライブサージャリーという
手術の実演がありました。
■ ■
そこへ行って驚いたのは、
中国でも二重、豊胸、脂肪吸引という
美容外科手術が盛んなことでした。
中国全土から、
富裕層のお金持ちがやって来て、
手術を受けていました。
病院には、
美容外科のフロアーがありました。
そこだけは、
内装が豪華で…
待合の椅子も革張りのソファーでした。
■ ■
一般の外来が、
失礼ながら、
かなり昔の日本の病院というイメージだったので、
その乖離(かいり)に驚きました。
中国は、日本以上に
『美』を追求する国である、
という印象を受けました。
■ ■
私は、
実際に歌った楊沛宜(Yang Peiyi)ちゃん(7)
を気の毒に思いました。
とても可愛らしい少女だと思います。
AFP NEWSでは
丸顔で歯並びがあまりよくなかったため、
中国の正しいイメージを表現していないとして、
中国政府が置き換えを命じた。
とありました。
7歳と9歳では骨格の成長も違います。
歯列矯正だけで十分美人になれます。
どうかめげずに成長してほしいと願っています。

2002年、上海にて
医学講座
血液検査
札幌美容形成外科では、
手術を受けていただく前に
血液検査をしています。
これは、
私が総合病院の形成外科医として、
働いていた時から同じです。
歯医者さんで抜歯をする時には、
血液検査をしないようですが、
病院の形成外科では…
血液検査をしてから手術をするのが、
日本ではふつうです。
■ ■
血液検査の内容です。
CBC(シービーシー)という、
全血球計算で、
血液中の
赤血球、白血球、血小板
を調べます。
生化学検査というのもしています。
肝臓や腎臓の機能をチェックします。
血糖値も調べます。
■ ■
梅毒、
B型肝炎
C型肝炎、
HIV(エイズ)、
などの感染症の検査もします。
手術をして、
血が止まらなかった困るので、
凝固系検査というのもします。
幸いなことに…
私が今までに検査をした、
1万例以上の検体で、
HIV陽性となった例はありません。
■ ■
検査結果が出て、
手術ができないこともあります。
昨日書いた…
糖尿病で手術ができない方。
札幌美容形成外科の検査で、
はじめて糖尿病が見つかった方。
数は多くありませんが、
未治療の糖尿病患者さんが、
まだ、かなりいらっしゃると思います。
■ ■
一番多い検査値異常は、
鉄欠乏性貧血です。
札幌美容形成外科は、
女性のお客様が多いので…
当然といえば、当然の結果です。
軽度の鉄欠乏性貧血でしたら、
手術は可能ですが、
鉄剤(てつざい)という、
鉄が入った錠剤を内服していただきます。
■ ■
女性は、生理で血が失われるために
どうしても貧血傾向になります。
消化管から、
目に見えないような出血があることも
考えられます。
サプリメントで鉄を補給しようとしても、
お金ばかりかかって、
効率的に摂取できません。
食生活に問題がある女性も
鉄欠乏性貧血になります。
データーによっては、
専門医をご紹介しています。
■ ■
お酒の飲みすぎで
肝機能障害になっている方もいます。
自覚症状がないために、
知らずにお酒を飲み続けると
入院が必要になることもあります。
男性に多いのが
高尿酸血症です。
痛風という病気になります。
血液検査の結果は、
簡単な説明の紙と一緒に
封筒に入れてお渡ししています。
ささやかなサービスです。
検査は
BMLという一流の検査会社に検査をお願いしています。
医学講座
糖尿病とキズの治り
糖尿病とは、
オシッコに糖が出る病気です。
血液の中に、
どの位、ブドウ糖が含まれているか?
という数値を血糖値(けっとうち)といいます。
ふつうは食後に高くなります。
糖尿病の患者さんは、
血糖値が正常の数倍にもなります。
そうすると、
多くなった分がオシッコに出てしまいます。
■ ■
難しく説明すると…
インスリンという
膵臓から放出されるホルモンが
少ないと血糖値が上がります。
インスリンは糖を細胞に取りこみ、
エネルギーにする作用をします。
ふつうは、食事をすると、
膵臓からインスリンが出て血糖を下げます。
■ ■
糖尿病になると…
キズの治りが悪くなります。
糖尿病で血管がもろくなり、
血液の循環が悪くなるためです。
また、糖尿病になると、
バイ菌に弱くなります。
すぐに化膿しやすくなります。
これも…
糖尿病でキズが治りにくい原因です。
■ ■
糖尿病になると…
神経も障害されます。
感覚が悪くなります。
ちょっとケガをしても、
痛みを感じなくなります。
そうすると…
小さなケガを繰り返すことになります。
神経が障害されて、
男性ではインポテンツになることもあります。
■ ■
糖尿病の方に多いのが、
足のケガです。
感覚がないので…
ケガをしやすく、
化膿しやすいので悪くなります。
血液の循環が悪いので…
キズの治りも悪いのです。
糖尿病が原因で、
足を切断することもあります。
■ ■
美容外科のように、
緊急を要さない手術は、
糖尿病がコントロールされていないと、
施術しないのが医師の常識です。
困るのが、
本人も自覚していない糖尿病です。
手術をしてしまってから、
キズの治りが悪くて
気づくのでは遅いのです。
■ ■
糖尿病でも、
しっかりコントロールしていれば、
手術を受けることはできます。
札幌美容形成外科では、
信頼できる糖尿病専門医を
ご紹介しています。
糖尿病が原因で
失明したり、
人工透析になる方もいらっしゃいます。
家系に糖尿病の方がいる方…
メタボ体型の方は
一度は検査を受けることをおすすめします。